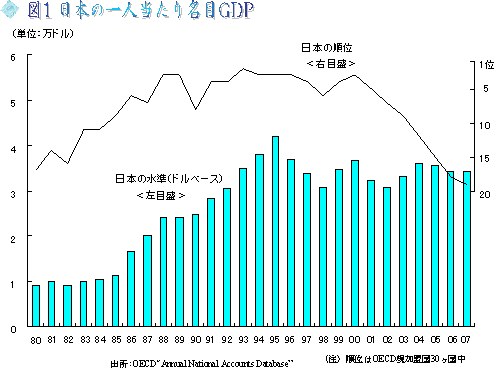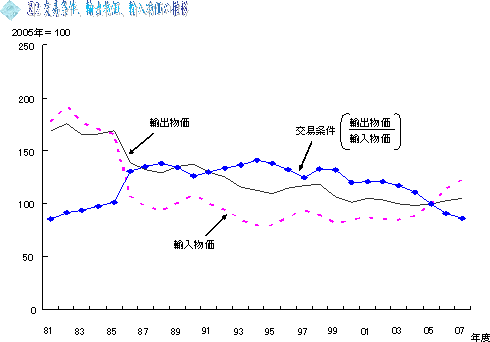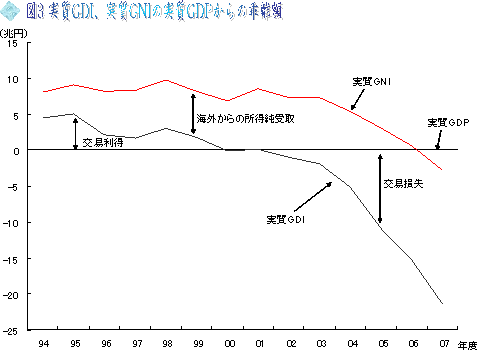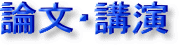
シリーズ「国民生活重視の経済政策を考える」
Ⅳ. 経済政策の戦略目標は企業の生産ではなく国民の所得 ―『軍縮』(2009年3月号、No.340、H21.2.7)
前回のシリーズのⅢで見たように(このHP<論文・講演>雑誌”シリーズ「国民生活重視の経済政策を考える」Ⅲ.「改革」が何故国民生活を苦しめるのか”H21.1.7参照)、「小泉改革」は本来の「構造改革」ではなく、その結果、シリーズのⅡで見たように(”Ⅱ.輸出に偏り過ぎた経済運営の咎め”H20.12.10参照)極端に輸出に偏り、内需の沈滞した日本経済を作り出し、シリーズのⅠで述べたような(”Ⅰ.四重苦に悩む国民生活の現状”H20.11.10参照)国民生活の四重苦を生み出した。最終回となる今回のⅣでは、国民生活を重視した経済政策こそが、日本経済を蘇らせることを述べてみたい。
日本経済の国際的地位は劇的に沈下
01年から08年までの小泉・安部・福田・麻生と続いた自公政権の経済的帰結を最も端的に物語る事実は、日本経済の国際的地位の劇的な沈下である。
図1に示したように、かつて日本の一人当たり名目GDPは、OECD加盟国内の順位で80年から徐々に上昇し、88年に3位に達した。その後10数年間は高水準を保ち、93年には2位、00年にも3位を維持していたが、その後の7年間に急落し、07年には19位となってしまった。この7年間に日本以外の国は全て一人当たり名目GDPが増えているのに、図1に明らかなように日本だけは減っているのである。
01年以降の国際的地位の劇的な沈下については、既にこのシリーズのⅠ~Ⅲで述べたことから原因は明らかであろう。「小泉改革」の下で、①日本の実質GDPの成長率はOECD加盟国平均よりも低く、②総需要デフレーターよりも輸入デフレーターの方が大きく上昇したので、前者から後者を引いたGDPデフレーターは低下し、③円安が続いてドル換算の名目GDPは更に小さくなったからである。
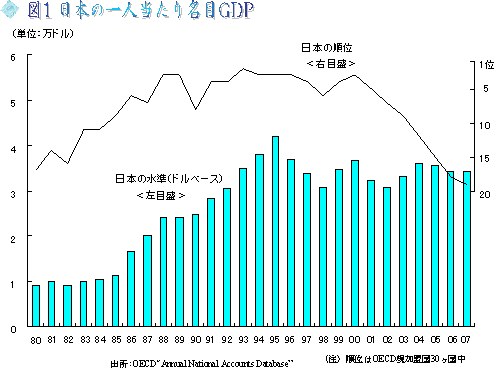
交易条件が急激に悪化
小泉政権以降の自公政権下で、もう一つ国民生活から見て、由々しい事態が起こっていた。それは、国民生活の基盤である「実質国内総所得(GDI)」や「実質国民総所得(GNI)」の伸びが、「実質国内総生産(GDP)」の伸び、つまり経済成長率よりも低かったのである。GDPで見ている以上に、国民総所得の停滞が大きく、これが国民生活沈滞の大きな背景になっているのである。
少し専門的になるが、国内で生産された付加価値の総額を実質ベースで測ったものがいつも聞きなれている「実質国内総生産(GDP)」である。しかし、この国内総生産を海外に安く売り、海外の生産物を高く買っていると、「国内総所得(GDI)」は減ってしまう。この輸出価格と輸入価格の比率を「交易条件」と言い、輸出価格の方が相対的に値上がりしていれば、交易条件は好転(「交易利得」の発生)、逆に比率が低下していれば交易条件の悪化(「交易損失」の発生)である。
図2は、企業物価指数のうちの輸出物価、輸入物価、両者の比率である交易条件を折れ線グラフで描いたものである。最近のところを見ると、02年から07年にかけて、交易条件が急激に悪化していることが分かる。
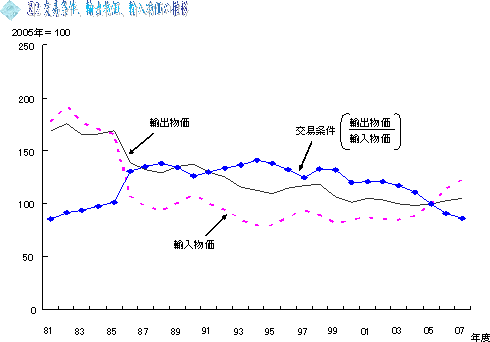
国民生活の基盤である国民総所得が減少
「実質国内総生産(GDP)」に「交易利得」を足した(又は「交易損失」を引いた)のが、「実質国民総所得(GDI)」である。このGDIに、更に「海外からの所得(純受取)」を加えたのが、「実質国民総所得(GNI)」だ。これこそが国民生活の基盤である。ここで「海外からの所得」というのは、対外投資からの受取所得と対内投資への支払所得の差額である。日本は毎年の経常収益黒字の累積で巨額の対外資産超過となっているので、所得の純受取は07年度で実質18兆円を超える。
さて、実際の実質GDPから実質GDIと実質GNIがどれだけ乖離しているかを、94年度から07年度まで描いてみると、図3の折れ線グラフのようになる。図2で見た通り、02年度以降毎年交易条件が悪化しているため、それまでの交易利得が交易損失に変わって実質GDIは実質GDPよりも下方に乖離し、乖離額はどんどん拡大して07年度には21兆円に達した。実に実質GDP五六二兆円の三・八%が失われているのだ。
他方、海外からの純受取は、日本の対外資産超過額の累積につれて毎年拡大し、07年度には18兆円に達しているが、交易損失の21兆円を埋め切れず、遂に実質GNIまで実質GDPより少なくなってしまった。
このように02~07年度に交易損失が拡大したのは、この間に円安が進んだことによる面が大きい。為替相場の変動は、仮に輸出価格と輸入価格が為替相場を反映して同じ比率で変動しているならば、交易条件を変化させない。しかし日本の場合、実際には輸入価格は現地の相場が基本となっていることが多いので、日本着の輸入品の価格は為替相場を反映して大きく変動する。これに対して、日本発の輸出品の価格は日本国内の相場が基本となっているので、日本着の輸入品の価格ほどには為替相場を反映して変動しない。このため、円高のときは輸入物価の下落が輸出物価の下落よりも大きくなって交易条件は好転し、円安の時は輸入物価の上昇が輸出物価の上昇よりも大きくなって、交易条件は悪化する。
02~07年度の場合は、円安に加え、更に原油、穀物、鉱石類などの国際商品市況が高騰したため、輸入物価の上昇は一層大きくなり、交易損失はそれだけ大きくなって、実質国内総所得と実質国民総所得を減らし、国民生活の基盤を揺るがせたのである。
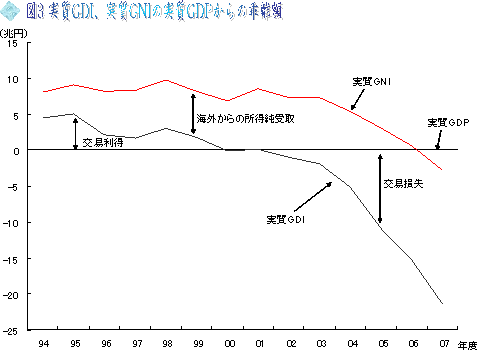
生活重視の戦略目標は国内総生産ではなく国民総所得
国民生活重視の経済政策の戦略目標は、実質国内総生産(GDP)ではなく、実質総所得(GNIやGDI)である。円安を進め、輸出で実質GDPの成長率を高めてみても、円安で交易条件が悪化しては実質総所得は減少し、国民生活は向上しないからだ。交易利得を拡大し、また対外資産の運用を効率化して海外からの所得の純受取を増やし、国民生活の基盤である実質総所得の伸びを高めていくことが、マクロ経済政策の戦略目標である。
交易利得を維持、拡大するには、小泉政権以来の「財政緊縮、金融超緩和」のポリシーミックスを転換し、財政は無駄を排除しながら国民生活支援の支出を増やして「中立」に戻し、金融は超低金利を改めて「正常」に戻さなければならない。「財政中立、金融正常」のポリシーミックスこそが、Ⅱ(前々回)の図3に示した「格差拡大と国内需要停滞のメカニズム」を逆転させ、格差の縮小する国民生活主導型の経済成長と「強い円」を実現する。
海外からの受取所得の増加は、「強い円」をバックに円を国際化し、「円建ての対外資産」を増やし、また対外資産の運用効率を高めることによって実現する。日本の企業が「強い円」をバックに対外直接投資を増やし、投資の収益率を高めることも貢献する。
国民生活支援の財政刺激は、出産・子育ての補助金拡大、学費の無償化、ガソリン税・自動車重量税の暫定税率廃止、地方高速道路の無料化、失業者・低所得者に対する負の所得税、低炭素社会を目指す環境対策やエネルギー効率向上、代替エネルギー開発への補助金、関連公共投資の拡大などが考えられる。
日本では、財政支出を拡大すると、長期金利の上昇(クラウディング・アウト論)や将来の増税を予想した貯蓄増加(マクロ合理的期待仮説)が起きるので、総需要拡大の効果はないと主張する人が多いが、これは間違っている。大幅な貯蓄超過で低成長に陥り巨額の対外黒字を持つ日本では、クラウディング・アウトは起きない。財政支出が増えれば国民が将来の増税を予測して所得増加を全部貯蓄に回すと言うのも、机上の空論である。
日本経済が米欧より先に立ち直る条件
現在、米国発の金融危機で世界経済の拡大が大きく減速し、日本は輸出の減少と、投資マインド、消費マインドの萎縮でマイナス成長に陥っている。
しかし、日本は米欧先進諸国と異なり、国内には住宅価格のバブル崩壊や、証券化商品・派生商品の値下がりに伴う金融危機は存在しない。従って、米欧のような国内要因による不況長期化のリスクはないのだ。この日本と米欧の違いで円高が進んでいるのである。円高は、目先では日本の輸出にとって不利であるが、長い目で見れば、既に見たように日本の交易条件を好転させ、交易利得を拡大して国民生活の基盤である実質総所得を増やす。世界不況に伴う国際商品市況の軟化も、日本の交易条件好転を後押しする。
現在、米欧の不況に伴う輸出の減少がもたらした実質国民総生産の縮小の方が、交易利得拡大に伴う実質国民総所得の拡大よりも強い。しかし、国民生活支援の財政政策が適切に打たれるならば、交易利得や海外からの所得純受取の拡大と相まって、日本経済と国民生活が米欧よりも先に立ち直ることは、決して夢ではない。
中国、インドなどのアジア諸国や中東、中南米などが、日本と同じように内需中心に立ち直ってくれば、これら諸国との相互貿易も加わって、米欧に依存せずに世界経済の再発展が始まる道も開けてくるであろう。
![]()
![]()