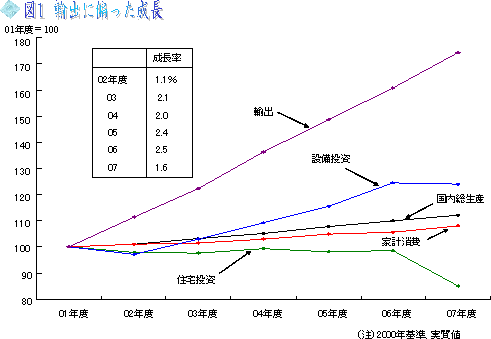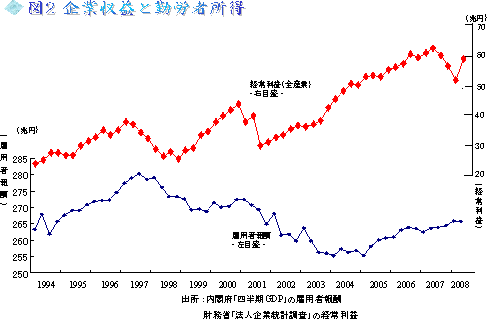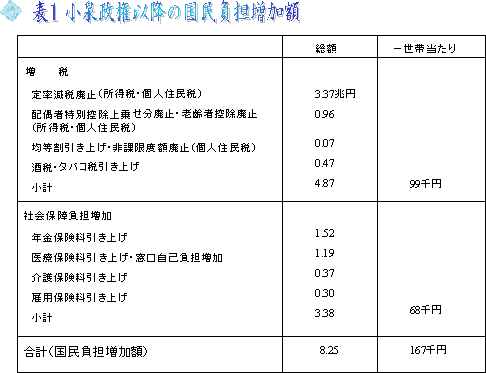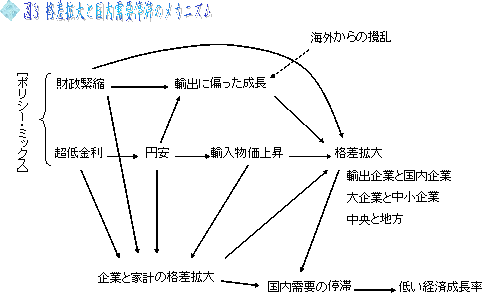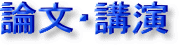
僔儕乕僘乽崙柉惗妶廳帇偺宱嵪惌嶔傪峫偊傞乿
嘦. 桝弌偵曃傝夁偓偨宱嵪塣塩偺欓傔丂乗亀孯弅亁乮2009擭1寧崋丄No.338丄H20.12.10乯
丂丂丂丂丂
丂慜夞偼丄崙柉惗妶偑巐廳嬯偵擸傑偝傟偰偄傞尰忬偵偮偄偰徻偟偔弎傋偨(偙偺HP亙榑暥丒島墘亜嶨帍乭僔儕乕僘乽崙柉惗妶廳帇偺宱嵪惌嶔傪峫偊傞乿嘥.巐廳嬯偵擸傓崙柉惗妶偺尰忬乭H20.11.10嶲徠乯丅崱夞偼丄壗屘偦偆側偭偨偺偐傪丄峫偊偰傒傛偆丅
桝弌婇嬈偩偗偑塰偊偨惉挿
丂擔杮宱嵪偼丄01擭搙偵亅0.8亾惉挿偵娮偭偨偺傪嵟屻偵丄02擭搙偐傜07擭搙傑偱偺榋擭娫偼堦娧偟偰僾儔僗惉挿傪懕偗偨丅偲偔偵03擭搙偐傜06擭搙傑偱偺巐擭娫偼丄恾1偺拞偺昞偵帵偟偨傛偆偵丄2亾戜惉挿偲側偭偨丅偙傟偵傛偭偰婇嬈偺廂塿偼夞暅偟丄擔杮嬧峴偺乽抁娤乿偵傛傞偲丄戝婇嬈偺攧忋崅宱忢棙塿棪偼僶僽儖婜偺僺乕僋傪忋夞傞偵帄偭偨丅僶僽儖偺曵夡埲崀丄廫擭埲忋傕堷偒偢偭偰棃偨婇嬈偺乽嶰偮偺夁忚乿丄偡側傢偪愝旛丒屬梡丒嵚柋偺夁忚傕丄04擭崰偵偼夝徚偟偨丅
丂偙偺傛偆偵擔杮宱嵪偼棫偪捈偭偰偒偨偺偵丄崙柉惗妶偼壗屘偄傑傕偭偰巐廳嬯偵嬯偟傫偱偄傞偺偱偁傠偆偐丅偦傟傪夝偔戞堦偺尞偼丄恾1偺拞偵嵼傞丅恾1偼丄宨婥夞暅偺捈慜偱偁傞01擭搙傪100偲偡傞巜悢偱丄崙撪憤惗嶻乮俧俢俹乯偲偦偺庡側撪栿偱偁傞桝弌丄愝旛搳帒丄壠寁徚旓丄廧戭搳帒乮偄偢傟傕幚幙抣乯偺悇堏傪丄07擭搙傑偱昤偄偨傕偺偱偁傞丅
丂堦尒偟偰柧傜偐側傛偆偵丄桝弌偑偙偺榋擭娫偵幍妱埲忋傕怢傃偰丄惉挿乮崙撪憤惗嶻偺憹壛乯傪堷偭挘偭偰偄傞丅師偵愝旛搳帒偑擇妱嫮怢傃偰偄傞偑丄桝弌偺怢傃偵斾傋傟偽掅偄丅偙傟偼丄桝弌偵娭楢偟偨愝旛搳帒偩偗偑戝偒偔怢傃偰丄崙撪廀梫偵娭楢偟偨愝旛搳帒偼偁傑傝怢傃偰偄側偄偐傜偱偁傞丅
丂偦傟傕偦偺敜偱丄崙撪廀梫偺拞怱偱偁傞徚旓巟弌偼偙偺榋擭娫偵8亾偟偐怢傃偰偄側偄丅廧戭搳帒偵帄偭偰偼15亾傕尭偭偰偄傞丅傑偨偙偺僌儔僼偵偼彂偄偰偄側偄偑丄岞嫟搳帒偼偙偺榋擭娫偵37亾傕棊偪偰偄傞偺偩丅
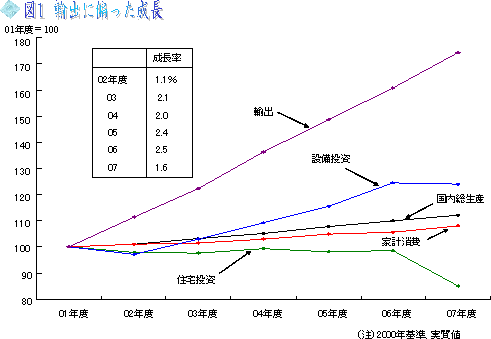
婇嬈廂塿偲嬑楯幰強摼偺奿嵎奼戝
丂壗屘崙撪廀梫丄偲偔偵偦偺拞怱偵偁傞壠寁徚旓偼丄尦婥偑側偄偺偱偁傠偆偐丅晛捠側傜偽丄桝弌婇嬈偑塰偊傟偽丄桝弌婇嬈偑屬梡傪憹傗偟丄捓嬥傪堷偒忋偘傞偺偱丄壠寁偺強摼偑憹偊丄徚旓巟弌傗廧戭搳帒傕憹偊偰棃傞丅偦偆偡傟偽丄崙撪婇嬈偺廂塿傕夞暅偟丄偦偙偱傕愝旛搳帒偺憹壛傗屬梡丒捓嬥偺夞暅偑婲偒丄峏偵徚旓巟弌傗廧戭搳帒偑憹偊傞偲偄偆岲弞娐偑惗傑傟偰丄崙柉惗妶偑岦忋偡傞丅
丂偲偙傠偑丄嵟嬤榋擭娫偺宱嵪惉挿偺拞偱偼丄桝弌偑怢傃偰偄傞偵傕峉傜偢丄偙偺傛偆側崙撪廀梫偺岲弞娐偵壩偑拝偐側偐偭偨丅
丂偦偺尨場偼丄恾2傪尒傟偽柧傜偐偱偁傞丅婇嬈偺宱忢棙塿乮慡嶻嬈乯偼丄02擭偐傜偳傫偳傫夞暅偟偰偄傞偑丄屬梡幰曬廣乮嬑楯幰偺強摼乯偼04擭傑偱壓偑傝懕偗丄05擭偐傜娚傗偐偵夞暅偟巒傔偨傕偺偺丄01擭埲慜偺悈弨偵傕栠偭偰偄側偄丅偮傑傝丄桝弌憹壛偑撪廀奼戝偵壩傪拝偗傞岲弞娐偺嵔偑丄婇嬈廂塿偺憹壛偐傜嬑楯強摼偺憹壛偵偮側偑傞強偱愗傟偰偄傞丅
丂婇嬈偼僶僽儖偺曵夡埲屻丄乽嶰偮偺夁忚乿偺堦偮偱偁傞屬梡偺惍棟傪恑傔偰偒偨偺偱丄02擭偐傜巒傑偭偨宨婥夞暅偺拞偱丄忢梡屬梡傪憹傗偟巒傔偨偺偼傛偆傗偔04擭偵側偭偰偐傜偱偁偭偨丅恾2傪尒傞偲丄偙偺擭偵傛偆傗偔嬑楯幰強摼偺尭彮偑巭傑偭偰掙傪攪偭偰偄傞偺偼丄偦偺偨傔偩丅峏偵05擭偵側傞偲丄傛偆傗偔堦恖摉偨傝偺捓嬥偑忋偑傝巒傔丄恾2偺嬑楯幰強摼傕忋偑傝巒傔偨丅偟偐偟丄偦偺夞暅僥儞億偼嬌傔偰娚傗偐偱偁傞丅偙傟偼丄捓嬥扨壙偑崅偔幮夛曐尟椏晧扴傕偁傞乽惓乿幮堳偺屬梡傪婇嬈偑嬌椡梷偊丄捓嬥扨壙傕埨偔幮夛曐尟椏晧扴傕柍偄僷乕僩丄擔屬偄丄攈尛丄埾戸側偳偺乽旕乿惓幮堳傪憹傗偟偰偄傞偨傔偱偁傞丅
丂偙偺傛偆偵偟偰惗傑傟偨婇嬈廂塿偲嬑楯幰強摼偺奿嵎偙偦偑丄崙柉惗妶偺岦忋偲崙撪廀梫偺惙傝忋偑傝傪寚偄偨宨婥夞暅傪惗傒弌偟偨偺偱偁傞丅
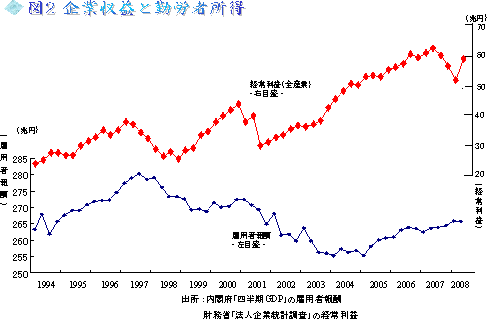
崙撪廀梫傪埑敆偟懕偗偨惌晎
丂偙偺傛偆側宨婥夞暅僷僞乕儞偲側偭偨帠偵偮偄偰偼丄惌晎偵傕愑擟偑偁傞丅
丂彫愹丒埨攞丒暉揷偲懕偄偨惌尃偼丄嵿惌愒帤偺奼戝傪杊偖偨傔丄慜弎偺傛偆偵岞嫟搳帒傪嶍尭偟偨忋丄崙柉晧扴乮崙柉偑晧扴偡傞惻嬥偲幮夛曐忈旓乯傪憤妟偱8.25挍墌丄堦悽懷摉偨傝偱16.5枩墌憹壛偝偣偨丅
丂昞1偼丄庡側崙柉晧扴憹壛偺撪梕偲偦偺崌寁傪帵偟偨昞偱偁傞丅憹惻崌寁偼4.87挍墌乮堦悽懷摉偨傝9枩9愮墌乯丄幮夛曐忈晧扴憹壛偺崌寁偼3.38挍墌乮摨6枩8愮墌乯偱偁傞丅
丂崙柉晧扴偺堷偒忋偘8.25挍墌乮堦悽懷摉偨傝16枩7愮墌乯偲丄岞嫟搳帒偺嶍尭13.7挍墌乮幚幙俧俢俹儀乕僗丄01乣07擭搙乯偼丄偨偩偱偝偊嬑楯幰強摼偺夞暅偑抶乆偲偟偰偄傞帪偵丄崙撪廀梫傪捈寕偟偨丅恾1偵尒傞傛偆偵丄徚旓巟弌傗廧戭搳帒側偳偺崙撪廀梫崁栚偑怢傃側偐偭偨偺偼摉慠偱偁傞丅
丂崙撪廀梫偑庛偄偨傔偵丄徚旓幰暔壙偼慜夞偺恾2偵帵偟偨傛偆偵丄07擭拞崰傑偱傎傏墶攪偄偱悇堏偟偨丅偙偺偨傔惌晎偼僨僼儗乮暔壙偺帩懕揑壓棊乯傪怱攝偟懕偗偨丅暔壙偺壓棊偱斕攧壙奿偑掅壓偟丄婇嬈廂塿偑埑敆偝傟偰晄嫷偵媡栠傝偟偰偼戝曄偩偲尵偆偺偱偁傞丅
丂偟偐偟丄尰幚偵偼恾2偵帵偟偨傛偆偵丄婇嬈廂塿偼憹壛傪懕偗偨丅偦傟偼丄慜夞偺恾2偺僌儔僼偱帵偟偨傛偆偵丄婇嬈暔壙偼04擭偐傜忋徃傪懕偗丄婇嬈廂塿偺埑敆側偳偼婲偙偭偰偄側偐偭偨偐傜偱偁傞丅
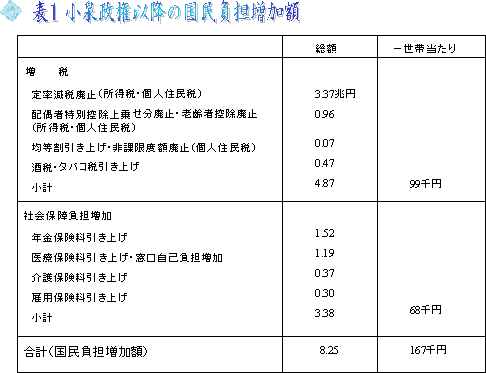
奺庬偺奿嵎奼戝偺儊僇僯僘儉
丂尒摉堘偄偺僨僼儗傪怱攝偟懕偗偨惌晎偼丄擔杮嬧峴偵懳偟丄弌棃傞尷傝挻掅嬥棙傪懕偗傞偙偲傪梫朷偟懕偗偨丅偦偺寢壥丄慜夞尒偨傛偆偵丄挻掅嬥棙偲偦傟偵敽偆墌埨孹岦偑懕偄偨偺偱偁傞丅挻掅嬥棙傕墌埨傕丄崙柉惗妶傪嬯偟傔傞偙偲偼丄慜夞徻偟偔弎傋偨偑丄桝弌婇嬈偵偼嬌傔偰桳棙偱偁傞丅墌埨偱桝弌昳傪埨偔攧傝丄桝弌悢検傪怢偽偡偙偲偑弌棃傞偟丄掅嬥棙偺偍偐偘偱帠嬈帒嬥傪掅僐僗僩偱挷払弌棃傞偐傜偱偁傞丅
丂偙偆偟偰丄崙柉惗妶丒崙撪廀梫偺捑懾偲桝弌偵曃偭偨宱嵪惉挿偲偄偆恾幃偑弌棃忋偑偭偨丅恾3偼丄偦偺場壥娭學傪帵偟偨僼儘乕僠儍乕僩偱偁傞丅
丂崙柉晧扴憹壛偲岞嫟搳帒嶍尭偲偄偆乽嵿惌嬞弅乿偲乽挻掅嬥棙乿偺慻傒崌傢偣乮億儕僔乕丒儈僢僋僗乯偼丄崙撪廀梫捑懾偵傛傞桝弌埑椡偲墌埨偵傛偭偰丄桝弌偵曃偭偨惉挿傪嶌傝弌偡丅崙柉惗妶偼丄嵿惌嬞弅亖崙柉晧扴憹壛丄挻掅嬥棙丄墌埨丄墌埨偵憹暆偝傟偨崙嵺彜昳巗嫷偺抣忋偑傝偵傛傞桝擖暔壙偺忋徃丄偺巐偮偵傛偭偰埑敆偝傟丄婇嬈偲壠寁偺奿嵎偼奼戝偟偰偄傞丅
丂岞嫟搳帒嶍尭丄桝弌偵曃偭偨惉挿丄桝擖暔壙偺忋徃丄崙柉惗妶偺捑懾偼丄崙撪廀梫偵埶懚偡傞婇嬈丄偲偔偵拞彫婇嬈偲丄偦傟傜偵埶懚偡傞抧曽宱嵪偵懪寕傪梌偊丄戝婇嬈偲拞彫婇嬈丄拞墰偲抧曽偺娫偵傕奿嵎傪惗傒弌偟偨丅
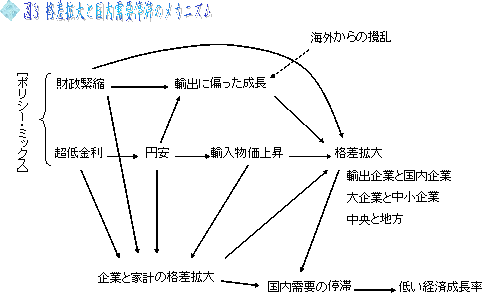
奀奜偐傜偺徴寕偵東楳偝傟傞擔杮宱嵪
丂偙偺傛偆側恾幃偺擔杮宱嵪偼丄崙撪偵惉挿偺巟拰偑側偄偺偱丄奀奜宱嵪偐傜偺徴寕偵偼嬌傔偰庛偄丅
丂偦偺戞堦攇偼丄愇桘傗崚暔側偳偺崙嵺彜昳巗嫷偺戝暆忋徃偲偄偆宍偱丄07擭偐傜08擭偵偐偗偰擔杮宱嵪傪廝偭偨丅偙偺偨傔丄徚旓幰暔壙偺忋徃偵傛傞崙柉惗妶偺埑敆丄桝擖尨嵽椏僐僗僩偺忋徃偵傛傞婇嬈廂塿偺埑敆偑婲偙偭偨丅擔杮宱嵪慡懱偺棫応偐傜尒傞偲丄奜崙昳傪崅偔攦偭偰崙嶻昳傪埨偔攧傞偲偄偆岎堈忦審偺埆壔偱偁傝丄擔杮偺強摼偑幐傢傟傞偙偲傪堄枴偡傞丅08擭4乣6寧婜偵丄壠寁徚旓傕婇嬈搳帒傕弮桝弌乮桝弌偲桝擖偺嵎乯傕慜婜斾儅僀僫僗偲側傝丄幚幙俧俢俹偼慜婜斾擭棪亅3.0亾偲戝暆側儅僀僫僗惉挿偵棊偪崬傫偩偺偼偦偺偨傔偱偁傞丅
丂戞擇攇偼丄僒僽僾儔僀儉儘乕儞栤戣偱偁傞丅廧戭壙奿偺忋徃傪尒崬傫偱掅強摼憌偵戄偟崬傑傟偨暷崙偺僒僽僾儔僀儉儘乕儞偼丄06擭偵廧戭壙奿偺忋徃偑僺乕僋傪懪偭偰壓偑傝巒傔傞偲丄偨偪傑偪夞廂崲擄偲側偭偨丅嬧峴偼偙偺廧戭儘乕儞傪徹寯壔偟偰墷暷側偳偺搳帒嬧峴丄徹寯夛幮丄惗曐夛幮丄奺庬偺僼傽儞僪側偳偵攧偭偰偄偨偺偱丄僒僽僾儔僀儉儘乕儞偺徟偘晅偒偼徹寯壔彜昳偺抣壓偑傝偲側傝丄偦傟傪曐桳偡傞嬥梈婡娭偺帒嶻偑尭壙偟巒傔偨丅夞廂崲擄偼廧戭儘乕儞堦斒偵傕峀偑傝丄攈惗彜昳傪娷傓嬥梈彜昳慡斒偺抣壓偑傝偵攇媦偟偨偨傔丄帒嶻尭壙偱帺屓帒杮偑晄懌偟偨傝丄悑偵偼嵚柋挻夁偱搢嶻偡傞嬥梈婡娭偑懕弌偟巒傔偨丅
丂岾偄擔杮偺嬥梈婡娭偼丄偙偺傛偆側儕僗僋偺崅偄嬥梈彜昳偵偁傑傝搳帒偟偰偄側偄偺偱丄嬥梈婋婡偺捝庤偼愺偄丅偟偐偟丄嬥梈婋婡偱悽奅宱嵪偑尭懍偡傞偨傔丄桝弌堦曈搢偺擔杮宱嵪偼9寧埲崀戝偒偔埆壔偟偰偄傞丅偙傟傪梊憐偟偰擔杮偺姅壙偼丄嬥梈婋婡偺捝庤偼愺偄偺偵丄捝庤偺怺偄墷暷彅崙偲摨偠傛偆側朶棊偵尒晳傢傟偰偄傞丅
丂彨偵桝弌偵曃傝夁偓偨宱嵪塣塩偺欓傔偑弌偰偄傞偺偱偁傞丅
![]()
![]()