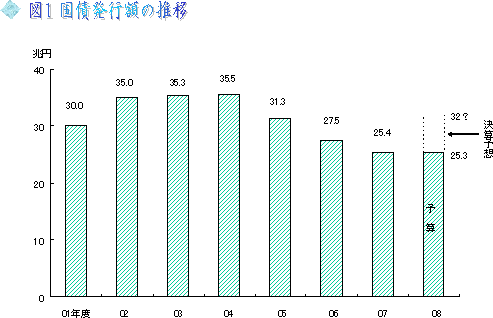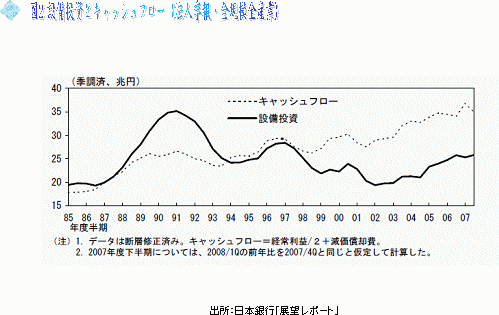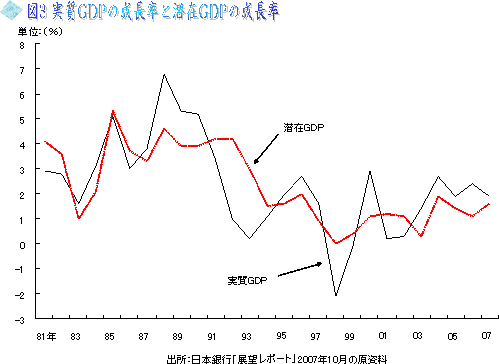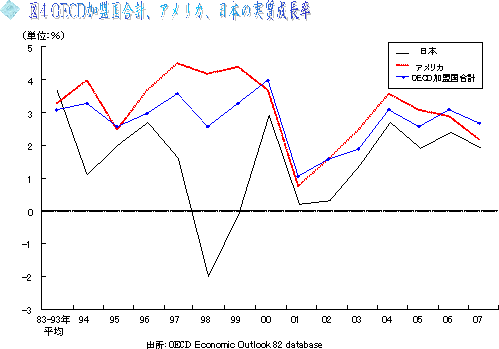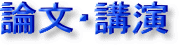
シリーズ「国民生活重視の経済政策を考える」
Ⅲ. 「改革」が何故国民生活を苦しめるのか ―『軍縮』(2009年2月号、No.339、H21.1.7)
このシリーズでは、一回目に四重苦に悩む国民生活の現状を述べ(このHP<論文・講演>雑誌”シリーズ「国民生活重視の経済政策を考える」Ⅰ.四重苦に悩む国民生活の現状”H20.11.10参照)、二回目にはその原因が輸出に偏り過ぎて国内経済を沈滞させた経済運営に在ることを指摘した(”Ⅱ.輸出に偏り過ぎた経済運営の咎め”H20.12.10参照)。今回の三回目では、「改革」を志向した筈の小泉内閣以降の自公政権が、どうしてこのような結果をもたらしたのかを考えてみよう。
「構造改革」の本来の理念
小泉内閣が志向した「構造改革」の本来の理念は、レーガン大統領の徹底した規制撤廃(レーガーミックス)によって基礎が作られ、クリントン・ブッシュ政権下の情報技術(ⅠT)革命とグローバル化によって開花した「新自由主義」「市場主義」の政策思想に基づいていた。経済を「小さくて効率的な政府」と「大きくて元気な民間」という構造に変えるために、政府介入の縮小と規制撤廃により、民間の自由競争を促進し、市場経済を活性化しようという考え方である。
事実、90年代の中頃から07年までの十数年間、米国経済はこの政策思想の下で長期繁栄を謳歌した(但し、その長期繁栄はいま住宅バブルの崩壊と金融システム危機によって終止符が打たれた。詳しくは最終回)。
小泉政権の経済運営、とくに「構造改革」は、この米国を手本にしてきた。毎年米国政府から送られて来る「対日年次規制改革要望書」に沿って「改革」を進めていたことが、その何よりの証拠である。そのため、竹中平蔵経済財政政策大臣は、頻繁に渡米して米国政府の要人と打ち合わせを行っていた。とくに、「郵貯・簡保」の民営化と「医療保険」の改革では、露骨な内政干渉まがいの圧力が米国から加わったことは、よく知られている。
それでは、小泉内閣は「構造改革」のために、どのような施策を実施し、その結果何が起こったのであろうか。
国民と地方の犠牲で財政緊縮を強行
まず「小さくて効率的な政府」を目指し、二つの手を打った。一つは財政の緊縮であり、もう一つは政府機関の民営化である。
財政の緊縮については、先ず小泉政権が編成する最初の予算、すなわち02年度予算の国債発行額を、前年度を下回る30兆円以下にすると公約した。実際は、01年度の不況で税収が予想以上に落ち込んだ上、景気対策の補正予算を組んだため、国債発行額は当初予算の30兆円を上回り、35兆円に膨らんだ。公約はあっさり放棄された。以後04年度まで35兆円台の国債発行が続いたが、05年度以降は、図1に示したように、年々国債発行額は縮小し、07年度は25兆円にとどまった。この3年間に10兆円減額したのである。
この国債発行の縮小は、景気回復で税収が伸びたことにもよるが、もう一つは、歳出削減、国民負担増加という財政緊縮を実行したからである。前回述べたように、小泉内閣以降の自公政権は、8.25兆円の国民負担増加(前回の表1参照)と実質GDPベースで13.7兆円の公共投資削減を実行した。この合計21兆円強の財政緊縮が無ければ、自公政権下の国債発行縮小はあり得なかった(但し、08年度の不況で国債発行額は再び30兆円以上に拡大しようとしている。表1参照)。
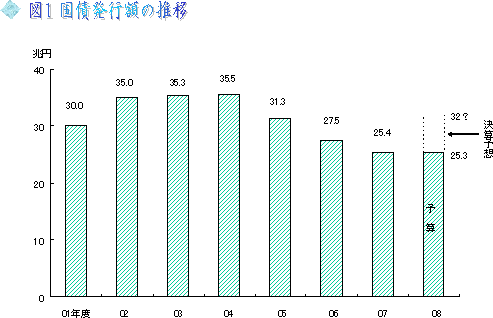
民営化は真の構造改革ではなかった
「小さな政府」を目指すもう一つの「改革」は、民営化である。小泉政権は、道路公団、郵政公社、政府金融機関の民営化を実行した。
しかし、道路公団は民営化したものの、高速道路の建設計画は、公団時代に決めた当初予定通りに実施させることになっている。また毎年度の高速道路建設計画は、民営化した後も政府が決定する。これでは形式は民営化したものの、内容は何も変わっていない。
郵政公社については、郵貯と簡保は典型的な「官業の民業圧迫」であり、郵貯は分割縮小し、簡保は廃止するのが、「小さくて効率的な政府」と「大きくて元気な民間」への道であるということが、多くの識者によって指摘されてきた。しかし、小泉内閣は、郵貯はそのまま郵貯銀行に、簡保はそのまま簡保生命にという形で民営化した。巨大な民営郵貯と民営簡保が相変わらず民業、とくに地方銀行、信用金庫、信用組合、農協、中小生保など地域密着型の中小金融機関を圧迫し続けている。ここでは、形の上で民営化されただけで、大きな政府の民間圧迫という構造は、なにも改革されずに残っている。
政府金融機関については、まず中小企業・農林漁業・国民生活・沖縄振興開発の四つの公庫と国際協力銀行の国際金融部門が合併して(株)日本政策金融公庫となり、政府金融機関のまま生き残る。その規模はメジャー・バンク並みであり、官業の民業圧迫は続く。また日本政策投資銀行と商工組合中央金庫は、株式会社となり、今後全民営化の予定だが、政府の指定により特定の対象に低利で融資する公的機能は残されている。二つの公庫と銀行のトップは民間から起用されたが、副総裁には従来通り所管官庁の官僚が天下っており、陣容は変わっていない。
以上のように、道路、郵政、政府金融は、形の上では民営化や合併、分割をしても、官業の肥大化、民業圧迫という内容は基本的に変わっていない。これは「構造改革」の理念に全く反している。構造を変えるのではなく、構造を維持するための化粧直しである。
的外れの規制緩和や超低金利
次に、「大きくて元気な民間」を目指し、小泉政権が実行したことは、規制緩和と超金融緩和の要請である。
しかし、小泉内閣の規制緩和によって民間市場経済が活性化した例を探すのは難しい。むしろ、派遣労働を製造業についても解禁したため、前回述べたように「非」正社員の割合が増加し、「正」社員と「非」正社員の間の不公平な格差が拡大したばかりではなく、前回の図2に示したように、企業収益と勤労所得の格差も拡大した。規制緩和が民間市場経済を活性化するどころか、内需停滞の大きな原因となっている。
小泉政権は、民間市場経済を刺激するため、日本銀行に対して超金融緩和・超低金利を少しでも長く続けるように要請し続けた。日本経済はまだデフレから脱却していないというのが、その口実であった。しかし、第1回目に図2を用いて説明したように、国内企業物価は04年から毎年2%程上昇しており、デフレで販売価格が下落し、収益を圧迫される心配などはなかった。その代わり、超低金利の副作用は、円安の行き過ぎと国民の預貯金の目減りに出ていた。
このような犠牲を払った超金融緩和・超低金利は、本来の目的である企業の設備投資を刺激することは出来なかった。図2に示したように、企業は設備投資を上回るキャッシュフロー(自己資金)を持っていたが、内需が停滞しているために、設備を積極的に拡大しなかったからである。
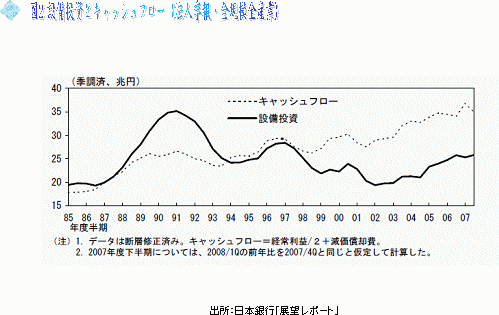
小泉「改革」で潜在成長力は高まらなかった
以上見てきたように、「小さくて効率的な政府」と「大きくて元気な民間」を目指した筈の小泉「構造改革」は、「羊頭狗肉」の民営化で民業圧迫をそのまま残し、財政緊縮で家計と地方経済を圧迫し、派遣労働の解禁で格差を拡大し、低金利と円安で家計所得を抑え続けて来たので、本来の「構造改革」とはならず、その成果は全く挙がらなかった。
その結果、小泉内閣が登場した01年以降今日まで、日本経済の供給サイドは改善されず、日本経済の潜在成長率(供給力で測った成長の能力)は上昇しなかった。
図3の折れ線グラフの点線は、潜在成長率の推移を示したものである。日本経済は、バブルが崩壊したあとも、93年頃迄は年率四%強の潜在成長率を維持していた。しかし、「失われた10年」の間に急落し、98年には一時ゼロ%近くに迄下がったが、その後は1~2%の潜在成長率が続いている。小泉内閣が発足した01年以降07年迄は、1.5%前後でほぼ横這いである。03年以降は、このような低い潜在成長率を現実の実質成長率が上回り、GDPベースの需給ギャップはやや縮小したが、この需要の伸びはもっぱら輸出増加に偏っていたため、潜在成長率を改善するような設備投資の伸びは起こらなかった。
このため日本経済の成長率は、図4に見るように、長期繁栄を謳歌した米国はもとより、OECD(経済協力発展機構)加盟国の先進国平均よりも低いままである。小泉「構造改革」の実効は、全く挙がっていなかった。
最終回となる次回には、このような日本経済を蘇えらせるためには、どのような経済政策を採ったらよいかを考えて、このシリーズの結びとしたい。
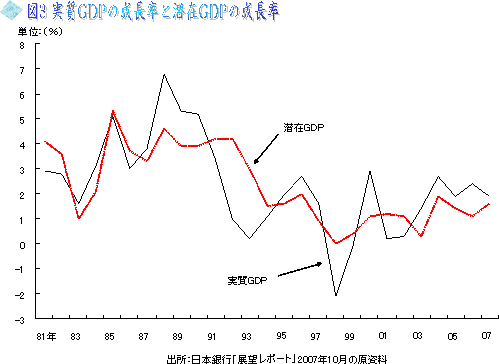
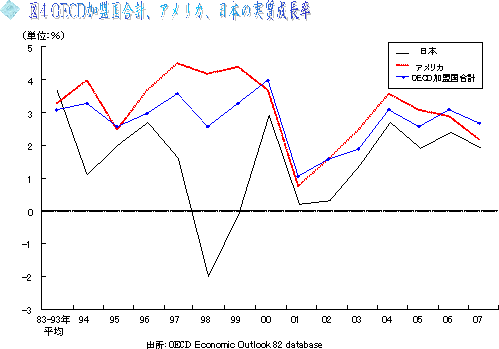
![]()
![]()