2007年9月版
円安バブルの崩壊と世界同時株安で景気の前途に不透明感
【「円安バブル」が遂に崩壊した】
対米ドルで125円、対ユーロで170円に迫る円安は行き過ぎであり、「円安バブル」の発生であるという見解を、2月頃からこのHPで何回も述べてきたが(例えば<最新コメント>“「上げ潮路線」は間違っている―野党は対立軸を、日銀は金利水準の正常化を)H19.2.21参照)、7月末から8月中頃にかけて、遂にこの「円安バブル」が崩壊した。一時は、対米ドルで110円、対ユーロで150円に迫る10%以上の急激な円高となった。
「バブルは壊れてみて始めてバブルであったと気が付く」と言うのはグリーンスパン前FRB議長の有名な言葉であるが、「この程度の円安はバブルではない」と見て、バブルの破裂で急激な円高が起きるリスクをヘッジしていなかった投資家は、大きな損失を蒙った。今年のBISの年報の警告が当たったと言うべきであろう(このHPの<最新コメント>“国際決済銀行(BIS)も円安の行き過ぎを「異常」と警告”H19.7.12参照)。
【サブプライムローン焦げ付きが世界同時株安と円安バブルの崩壊の引き金】
今回の「円安バブル」の崩壊は、円安を非難する外国の政府高官の発言が刺激になったのではなく、米国のサブプライムローン問題に端を発する信用不安と景気後退の懸念が引き金となった。
サブプライムローンは証券化され、世界中の投資家が保有している。このため、その焦げ付きリスクを誰がどの程度負担しているかが分らず、各国の金融システムで信用不安の疑心暗鬼が生まれた。
その結果、「flight to quality(質への逃避)」が発生し、世界中で株式から国債への資金シフトが起こり、世界同時株安となった。日本でも、日経平均で18千円台から16千円割れまで暴落した。
それと同時に、日本の円相場が、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、アジア諸国通貨など全ての通貨に対して、突如急上昇した。これはリスクに敏感になった投資家が、円安が逆転した時のリスクが怖くなり、我先に円キャリ取引の解消に走ったためである。この動きに遅れた投資家は、前述のように大きな損失を蒙ったのである。
【115円前後の円高は経済に大きな影響を与えない】
一連の動きは、今後の日本の景気にどのような影響を及ぼすであろうか。円高、株安、米国景気の三つに分けて考えてみよう。
円相場は、現在、対米ドルで115円前後で推移している。6月調査「日銀短観」における企業の想定為替レートは、07年度平均で114円40銭(下期は114円23銭)であるから、現在の円相場であれば事業計画と業績予想は変わらない。円安バブルが続いた場合に比較して、輸出依存度の高い企業の利益は減り、輸入依存度が高い企業の利益は増えることはあっても、全体としては6月短観で予想されている高い売上高経常利益率は変わらないと見るべきであろう。
円高の企業収益に対する影響を推計した調査を見ると、輸出サイドの損失ばかりを見ていて、輸入サイドの利益を見ていないものが多い。またグローバルに展開している企業は、輸出入を上手にバランスさせる事ができる。企業収益に対する円高の攪乱的影響は、個々のケースは別として、全体として見ればそれ程大きくないのである。
【世界経済の鍵を握る米国景気の動向】
次に世界同時株安の影響であるが、株安がどの程度持続するかを見極めないと、結論は出せない。ヨーロッパとアジアの実体経済は今のところ問題はないので、米国景気が立ち直るのであれば、各国の株価回復は時間の問題であろう。
しかし、米国の景気後退の兆しが出て来ると、その影響は日本を含む各国の経済、ひいては企業業績にも響くので、株価の回復は遅れ、逆資産効果で世界経済に悪影響が出て来るであろう。
そこで問題は米国景気である。サブプライムローン焦げ付きに端を発した金融市場の不安が、個人の消費態度など実体経済に影響を及ばすのか、FRBが今月中にも利下げに踏み切って景気後退を予防しようとするのか、など多くの不確定要因があり、現時点で結論を出すのは早過ぎる。
【法人企業統計の歪みで4〜6月期GDPの2次速報はマイナス成長か】
さて、日本の景気動向であるが、今回の一連の動揺の影響を受けた指標は、まだ出ていない。その直前の指標の中で注目される動きを見ていこう。
まず4〜6月期の実質GDP(1次速報値)は、前回の<月例景気見通し>(2007年8月版)で予測した通り、純輸出の成長寄与度がゼロとなったため、家計消費と設備投資の着実な増加のみに支えられて前期比+0.1%(年率+0.5%)の成長にとどまった(図表1参照)。
しかし、この程公表された4〜6月期の「法人企業統計」によると、設備投資が前期比−10.2%、前年同期比−4.9%と大きく落込んだ。前年同期比のマイナスは17四半期振りである。
この計数に基づいて、4〜6月期GDPの2次速報値が推計されるため、設備投資はプラスからマイナスへ下方修正され、それによって、実質成長率は10四半期振りにマイナスになる可能性がある。
【サンプル替えに伴う統計の歪みは困ったこと】
設備投資の1次速報値の基礎となった4〜6月期の一般資本財出荷は、前期比+2.1%、前年同期比+1.1%の増加である(図表2参照)。法人企業統計の設備投資は、この計数とあまりにも大きく乖離している。
実は、4〜6月期の法人企業統計では、年に1度のサンプル替えとして、調査対象の中小企業(資本金1億円未満)約9400社の全てを入れ替えた。この中小企業(主に非製造業)の設備投資が前年同期比−19.9%、非製造業全体が同−13.1%と大きく落込んでいるのである。これは、サンプル替えに伴う「統計の歪み」であって、実勢を現わしていないと思われる。
その「歪み」がGDP統計のような基本統計に反映されるのは困ったことである。早急にGDPの推計手法を改善するべきである。
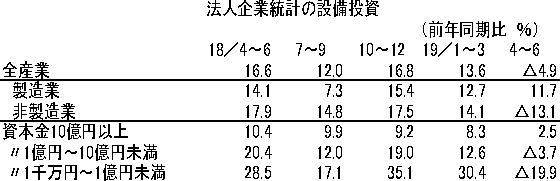
【地震の攪乱的影響を除けば鉱工業生産と出荷は緩やかに増加】
次に、7月の鉱工業生産と出荷は、中越沖地震の影響で自動車の生産・出荷が一時ストップしたため、前月比それぞれ−0.4%、−0.2%の減少となった(図表3参照)。因みに輸送機械工業の生産と出荷は、同−7.3%、同−10.2%の大幅下落である。この影響を除けば、7月の鉱工業生産と出荷はプラスである。
生産ストップの反動によって、8月の生産予測指数は前月比+6.8%の急上昇となっている(図表3参照)。9月は同−2.5%の減少となるものの、7〜9月期平均は前期比+4.1%の大幅増加である。実績はこの予測ほどには増加しないとしても、7月の減産は一時的で、鉱工業生産と出荷は引続き緩やかな増勢を維持していると見られる。
【雇用の改善と設備投資の増勢は続いている】
「法人企業統計」の歪みによって攪乱されている設備投資は、実勢としては、7月も着実な増加基調を保っている。7月の一般資本財出荷は、前月比+5.4%、前年比+3.7%の増加となった(図表2参照)。7月の水準は、4〜6月平均比+4.0%増の伸びとなっている。
7月は消費関連の指標がやや弱い。雇用者数は前年比+1.0%と着実に増加し、完全失業率は3.6%と前月比0.1%ポイントの改善をみたものの、名目賃金の前年比は−1.9%と下落幅を拡大し、可処分所得(勤労者世帯)と消費支出(全世帯)の前年比も、それぞれ−4.5%、−0.2%と前年水準を下回った(以上図表2参照)。
4〜6月期に足踏みとなった純輸出は、7月に入っても横這い傾向となっている。日銀推計の実質貿易収支は、7月も前月比0.0%、4〜6月平均比−0.2%となった。
【景気の前途には不透明感】
サブプライムローンの焦げ付き問題に端を発した円安バブルの崩壊と世界同時株安が、今後8月以降の景気指標にどのような影響を及ぼして来るかを見なければ何とも言えないが、景気の前途に不透明感が出て来たことは確かであろう。
しかし、統計の歪みによる攪乱を別にすれば、雇用と設備投資の増加は今のところ着実に進んでいる。来年に向かって米国景気の立ち直りがはっきりして来れば、実体経済に大きな動揺は生じないが、果してどうなるであろうか。