![]()
内外価格差縮小下の金融政策:利上げで円安修正を 物価は横這いでよい (『週刊東洋経済』2007年7月14日号)
消費者物価が上昇しないからといって、まだデフレ続いているとか、利上げをすべきではないと言うのは間違っている。物価下落や円安には別の理由があり、着実な利上げで正常な状態に戻すことが大切なのだ。
鈴木政経フォーラム
代表
鈴木 淑夫
最近の日本経済で、大変珍しい現象が二つ起こっている。一つは国内物価(消費者物価やGDPデフレータ)が下落傾向を辿っているのにも拘らず、為替市場では円安傾向が続いていることである。もう一つは国内企業物価が上昇しているのにも拘わらず、消費者物価が下落していることである。
普通、国内物価が下落傾向を辿れば、実質為替レートに変化がない場合、市場で観測させる名目の為替レートは円高になる筈である。それが逆に円安傾向を辿っているということは、実質為替レートが下落傾向を辿っていることを示している。
事実、日本銀行が推計し、『金融経済月報』で公表している円の実質実効為替レートは、95年頃をピークに最近まで急激な円安傾向を示している。直近の水準は、85年のプラザ合意直前の円安水準である。つまり、プラザ合意後、資産バブルの発生と崩壊という大きなコストを払ってまで進めた円高促進政策は、最近10年間ほどの間に帳消しとなり、実質実効ベースで円の水準は元に戻ってしまったのである。
もう一つの珍しい現象は、国内企業物価と消費者物価の逆乖離である。通常の価格体系では、サービス業と製造業の生産性上昇率格差を反映して、サービス料金を含む消費者物価が、製造業の製品価格を中心とする国内企業物価に対して、相対的に割高になって行く。高度成長期がその典型で、卸売物価が変動を繰り返しながら長期的にはほぼ安定していたのに対し、消費者物価は大幅な上昇傾向を示した。
高度成長が終わった後も、この傾向は続いており、92年頃から始ったデフレの期間も、国内企業物価の方が消費者物価よりも急激に下落し、消費者物価が相対的に割高になる価格体系の変化は続いていた。
ところが最近4年間ほどは、国内企業物価が上昇に転じたにも拘らず、消費者物価は微落傾向を続けている。価格体系の中で、珍しい逆乖離現象が起っているのである。
以上の二つの現象に共通する背景は、内外価格差の縮小傾向である。
OECDが加盟国の国内物価を用いて試算した購買力平価を見ると、95年時点で、円の購買力平価は対米ドルで一七五円であった。この年の円の市場相場は、IMFの統計によると九四円であったから、日本の国内物価は米国の国内物価に対して86%(一七五/九四)割高であった。実際、この頃に海外を旅行すると、海外の物価は安く感じられた。その代わり国内に戻ると、海外に較べて物価が高く、日本人の生活水準はあまり高くないことが実感できた。
図1に示したように、購買力平価はその後一貫して円高ドル安傾向を辿っているが、市場の円相場は変動を繰り返しながらもほとんど安定しているため、内外価格差は縮小傾向を示している。06年現在、円の購買力平価は対米ドルで一二四円であり、市場相場は一一六円なので、日本の国内物価の対米割高率は7%まで縮小した。今年は、今のところ市場相場が一二〇円を超えているので、恐らく内外価格差はほとんど解消してきたのではないか。
最近海外旅行をした日本人は、海外の物価が以前に較べて高くなったと感じていると思うが、それはこのような内外価格差の縮小を肌で感じているのである。
このような内外価格差の縮小は、日本経済にグローバル化の波が浸透してきたためである。製造業の製品価格は、輸出市場での競争や国内市場での輸入品との競合で、内外価格差は既に存在していない。しかし非貿易財であるサービス料金(小売マージンを含む)、地代・家賃などでは、明らかに日本が割高であった。しかし世界経済のグローバル化が進むにつれて、海外のサービス業(流通を含む)が日本に進出し、また内外のグローバル企業が立地を検討する際に、日本と海外の賃金、サービス料金、家賃・地代などを比較検討するようになった結果、賃金、サービス料金、家賃・地代などにも内外価格平準化の圧力が加わっている。
このため、製造業の製品価格以外の国内物価の割高が徐々に是正されている。その過程で、内外価格差の縮小と、消費者物価と国内企業物価の逆乖離が生じているのである。
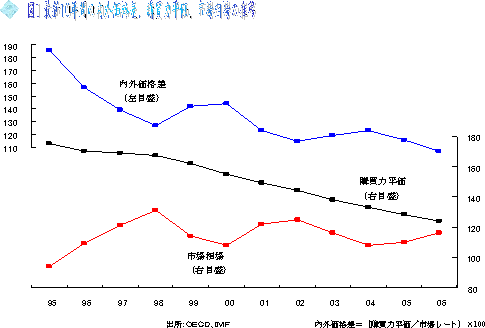
悪化する交易条件と一人当たりGDP
内外価格差の縮小は、二つのルートを通じて進行している。一つは、日本の国内物価そのものの下落であり、もう一つは為替相場の円安である。国内物価の下落と円安の併存は、前述の通り、日本円の実質実効レートを下落させている。日本が自国品を安く売り、外国品を高く買うという意味で交易条件の悪化である。
この10年以上にわたる交易条件の悪化は、日本に何をもたらしたか。円安によって輸出が増進し、日本経済は飛躍的に発展したのか。
そのような事はない。97〜02年には経済が停滞し、平均して年率〇・五%しか成長していない。97年の財政再建・緊縮政策の失敗、その後の金融危機対策の遅れと金融恐慌の発生などによる政策不況である。03年以降に至って民間企業の三つの過剰が解消し、輸出主導で平均して年率二%程度の緩やかな回復にようやく辿りついたのである。
安く売って高く買う交易条件の悪化は、むしろ日本経済発展の足かせとなっている。10年程前、例えば95年の日本の一人当たり名目GDPは、図2に示したようにピークであり、世界の順位はルクセンブルク、スイスに次いで第3位であった。海外旅行をすると、自分の所得に比して海外の物価は割安で、日本人は国際的に金持ちになったという実感があった。もっとも国内に帰ると物価が高いので、前述のように、実質所得が高くないことがよく分かった。
10年たった今日(05年現在)、日本の一人当たり名目GDPは、図2に示したように大きく低下し、世界第13位に転落してしまった。実質成長率が前述のように低かったうえに、国内物価(GDPデフレーター)が下落し、更に円安が進んだからである。海外を旅行しても、自分の実質所得は、海外物価で測っても高くないと感じられるようになった。
10年程の間に、日本の消費購買力がこのように低下してしまったことは、日本経済の発展にとって、明らかにマイナスである。
実質為替相場の下落=交易条件の悪化は、日本の一人当たり名目GDPというフローの面だけではなく、日本の企業の市場価値(時価総額)というストックの面でも、日本にとって不利である。外国から見ると、日本の企業の市場価値は安くなったので買収し易く、日本から見ると、外国の企業の市場価値は高くなったので買収し難いからである。
本年二月末の中国発世界同時株安のあと、中国はもとより、欧米の株価も値下がり分を埋めて更に上昇しているが、日本だけが戻りきれないでもたもたしている。株高に伴う資産効果が、日本だけ小さいのだ。海外投資家から見た外貨建の日本の株価が、円安に伴って割安となり魅力がないのが一因であろう。
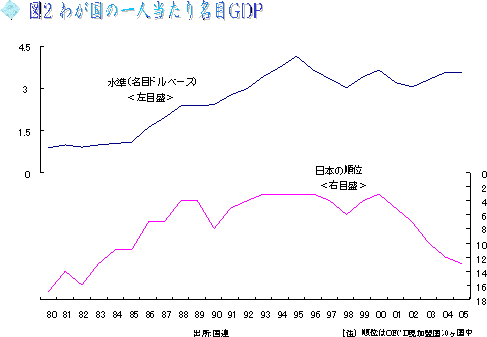
利上げは安倍政権に不利な話ではない
最後に、以上の分析から得られる政策的含意を考えてみよう。
日本ではこれ迄、国内物価の下落をデフレ、デフレと言って騒いで来た。確かに02年頃までの低成長の下で、国内の需給ギャップが悪化していた時期には、物価の下落が企業業績の一層の悪化を呼び、いわゆるデフレ・スパイラルが起きる危険性があった。従って、この時期の量的緩和・ゼロ金利政策は、金融システムに安心感を与える効果しかなかったとしても、適切であった。
しかし03年以降、潜在成長率(二%弱)を僅かに上回る平均約二%の成長により、需給ギャップは少しずつ縮小し始めた。とくに昨年10〜12月期(年率五・四%成長)と本年1〜3月期(同三・三%)の高成長により、内閣府も日本銀行も需給ギャップは需要超過に転じたと見ている。
こうなると、国内物価(消費者物価とGDPデフレーター)が上昇しないのは、国内の需給の反映ではなく、内外価格差縮小の反映である。
全国消費者物価(除生鮮食品)は、内外価格差が解消する迄は、なかなか上昇しないのが正常な姿であり、性急に二%程度の上昇を目指す現在の政府の政策姿勢は間違っている。無理に上げようとして利上げを遅らせれば、低金利下で非効率な投資が増え、資産バブルが発生するなど、持続的成長の基盤が崩れるであろう。また消費者物価を無理に上昇させれば、内外価格差縮小の圧力は円相場に片寄り、一層の円安が進むかも知れない。これも次に述べるように、持続的成長を脅かすものである。
現在の円安は、これ迄述べてきた内外価格差縮小の反映と、大幅な内外金利差が続くという市場の期待によって起っている。
ユーロ圏諸国の政府は、既に円安は行き過ぎていると不満を述べているが、米国議会でも、5月に円安に対する制裁の是非について、下院の公聴会が開かれた。またBIS(国際決済銀行)の『年次報告書』(06〜07年度版)でも、最近の円安は「明らかに異常」と指摘し、日本銀行の利上げ継続が為替市場正常化の助けになるとしている。
現在のところ、米国政府は円安を非難していないが、更に円安が進んで国内産業界の突き上げが強まれば、いつ変わるか分からない。そうなれば、円高が大きく進むことはないという期待に基づいて累積している円キャリ取引に、突然巻き戻しが起り、唐突な円高で経済が混乱する危険性がある。
日本銀行政策委員会は、6月調査『日銀短観』で下期の経済拡大を確認したのであれば、たとえ消費者物価が前年比で上昇していなくても、7月中に追加利上げを実施すべきであろう。そうなれば、年内にもう一回利上げして、政策金利が一%台に達するというシナリオが見えて来る。日本の金利についての市場の期待も変化し、行き過ぎた円安に歯止めが掛かるであろう。
前述のように、本年は内外価格差がほとんど解消しつつあるように見える。遠からず消費者物価の下落と円安の併存は止まるかも知れない。そうなれば、国民にとって最も望ましい正常金利・物価安定・円安修正(安倍政権は低金利・物価上昇・円安を志向)が実現する。金利水準正常化は経済情勢好転の証であって、政権に不利な話ではない。参院選に係わりなく、日本銀行は自信を持って政策を運営して欲しい。