![]()
政治圧力の中で問われる日銀の「情勢判断」 (『週刊東洋経済』2006年12月9日号)
名目GDP成長促進を前面に打ち出す安倍新政権は、その具体策乏しきゆえに超低金利持続を求める。一方、日銀は新日銀法下の独立性が試される局面だ。ただ、それだけに日銀の「情勢判断」の確かさが問われることになる。
日銀OBによる寄稿。
鈴木政経フォーラム
代表
鈴木 淑夫
安倍新政権の政策は、外交・防衛・教育などの面でかなりはっきりして来たが、税制改革を含む財政政策、社会保障政策、規制改革など経済政策については、経済財政諮問会議、税制調査会などの人事刷新が行われただけで、具体的な政策内容はまだよく見えていない。
その中で、経済戦略の柱が名目成長促進であることは、どうやらはっきりしてきた。日本の政府債務残高対GDP比率は、小泉政権下の上昇で、米国、カナダ、ユーロ地域の二倍に達し、予算に占める国債費のウェイトも膨張している。これを引下げるため、「今後五年間に一六兆円の財政赤字を削減して基礎収支の黒字化を図る」、という小泉内閣末期の「骨太方針(06年度)」は、安倍内閣に引継がれた。安倍内閣としては、税の自然増収を少しでも大きくし、歳出削減、国民負担引上げを少しでも軽くするため、名目成長を促進したいというのが動機である。
もともと財政赤字削減路線については小泉内閣の中に、名目成長促進派の竹中平蔵総務大臣(当時、以下同じ)・中川秀直自民党政調会長と、財務省の影響を受け低い名目成長を前提に厳しい増税を主張する与謝野馨経済財政大臣・谷垣禎一財務大臣の対立があった。結果は安倍新内閣の下で、中川新幹事長、竹中氏に近い太田弘子新経済財政大臣、本間正明新税調会長が実現し、与謝野氏と谷垣氏は政府・自民党の主要ポストを去った(与謝野氏は一度引受けた党税調会長を辞任)。名目成長促進派が財務省派を抑えたのである。
しかし、では、どうやって名目成長促進を図るのか。イノベーション促進と言っているが、これは時間もかかるし、効果も事前には予測し難い。設備投資促進税制や法人税実効税率の引下げが俎上にのぼっているが、明年の参院選後まで棚上げされた消費税率引上げを含む税制改革全体の姿は、まだ見えていない。そのため、日本銀行に対して出来るだけ長く超低金利を持続して、名目成長促進に協力して欲しいという政府・自民党の要請が見え隠れしている。
超低金利持続を求める政治圧力
こうした状況にあって、日本銀行は10月31日に『経済・物価情勢の展望(06年10月)』(以下『展望レポート』)を公表し、「極めて低い金利水準による緩和的な金融環境を当面持続しながら、経済・物価情勢の変化に応じて、徐々に金利水準の調整を行うことになると考えられる」と述べ、当面直ちに利上げはしないが、「経済・物価情勢の変化」次第で、極めて低い現在の金利水準を徐々に引き上げて行くという政策意志を示した。
利上げを決断させる「経済・物価情勢の変化」とは、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比上昇幅の拡大、設備投資行動の一層の強気化、海外経済情勢、特に米国と中国の上振れ、などであることが、『展望レポート』の文中から読み取れる。
要するに日本銀行は、政府・自民党の圧力にとらわれず、現在の異常に低い金利水準を、情勢次第で徐々に引上げて行くという政策意志を示したのである。
政府・自民党が名目成長促進のため、日本銀行に金融緩和、低金利の持続をあからさまに要請したことは、戦後少なくとも二回あった。列島改造・福祉元年予算の田中角栄内閣の時(以下「前々回」)と、ドル安阻止の国際協調下における宮沢大蔵大臣の時(以下「前回」)である。
二回とも日本銀行は政府・自民党の要請に引きずられて政策の転換が遅れ、前々回には大インフレの末の第一次石油ショックで物価狂乱に陥り、高度成長の終焉につながった。前回には地価・株価の資産バブルを発生させ、金融危機を伴う「失われた十年」となった。これは、戦後金融政策史上の二大失敗である。
この二大失敗と今日の姿を比較してみると、別表の通り政府・自民党と日本銀行の関係には似たところがある。動機こそ異なれ、政府・自民党が、名目成長促進のため、低金利の持続を要請している点である。
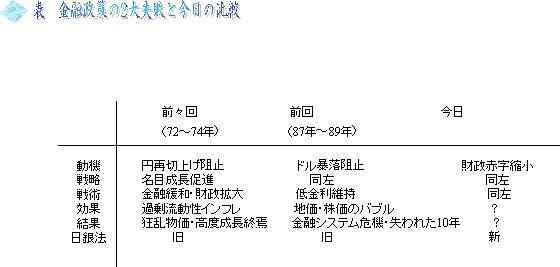
独立性を保障した新日銀法は”機能”するか
しかし相違点もある。一番大きいのは、98年に改正日本銀行法が施行され、政府と日本銀行の法的関係が変ったことである。1942年の戦時立法に、戦後49年になって、「木に竹を接ぐ」ように政策委員会の設置を埋め込んだ旧日本銀行法には、政府の金融政策に対する指示権と日銀総裁罷免権が残っていた。
しかし新しい日本銀行法では、政府の政策指示権が政策委員会に対する議決延期請求権に変わり、金融政策の独立性が確保された。政府の日銀総裁罷免は、総裁任命が国会承認人事であるために簡単ではなくなり、日本銀行の独立性は強められた。政策委員会の構成も、旧法では都長銀、地銀、産業、農業の各代表(実際は都長銀を除き大蔵又は日銀OB、通産OB、農林OB)四名と総裁の五名で構成され、議論は低調であった。これが新法では、審議委員六名(学者、エコノミストなど学識経験者)、総裁、二名の副総裁、合計九名で構成され、議論は活発で議事録の要旨も公開され、政策決定の透明性が高まった。
この新法の下で、今回は政府・自民党の要請に金融政策が引きずられることは無いのであろうか。
前々回には、逆らえば佐々木総裁を罷免するぞという田中総理の脅しが、政府・自民党の複数ルートから伝わって来たと聞いている。前回は私自身も理事であったが、逆らえば三重野康副総裁の総裁昇格はないという空気が、宮沢蔵相の周辺から様々のルートで伝わって来た。
政府に政策指示権がある以上、政府の承認なしに金融引締めに転じることは、総裁にとって辞表を懐にした罷免覚悟の行動でしかなかった。前々回と前回の総裁は、そのような混乱を避けた。
今日の新法の下では、政府に議決延期請求権しかない。政策を理由とする総裁罷免も、国会で大きな政治問題になるだけに簡単ではない。
しかし、08年3月に任期を迎える福井総裁と二人の副総裁の後任人事について、日本銀行に圧力をかけ、政策の駆け引きに使うことは不可能ではない。総理など政府・自民党の要人と総裁が気付かれずに接触する機会は、総理官邸で行われる経済財政諮問会議や月例経済閣僚会議などの前後に、いくらでもあるからだ。
逆に言えば、そのような機会を通じて、日本銀行の政策変更が、長い目で見て息の長い成長に通じ、財政赤字縮小を容易にすると説得し、信頼を得る器量が、いま福井総裁に求められているのかも知れない。
日銀の情勢判断は大丈夫か
そうだとすれば、あとは日本銀行の情勢判断と政策運営の能力如何である。『展望レポート』では、予測の上振れ、下振れのリスクをよく吟味しているが、ここでは二、三の気になる点を指摘したい。
『展望レポート』の中で、日本経済は、「需要超過状態」になっていると何回も述べているが、この判断は間違いないか。
日本銀行が『日銀レビュー』(06年5月)の中で自ら認めているように、その時点のデータで推計した潜在成長率の「リアルタイム推計値」は、その後のデータまで入れて推計した「最終推計値」に比べて、景気上昇期には過小推計となり、景気下降期には過大推計となる。この誤差は、別掲のグラフに示したように、年率一%にも達する。
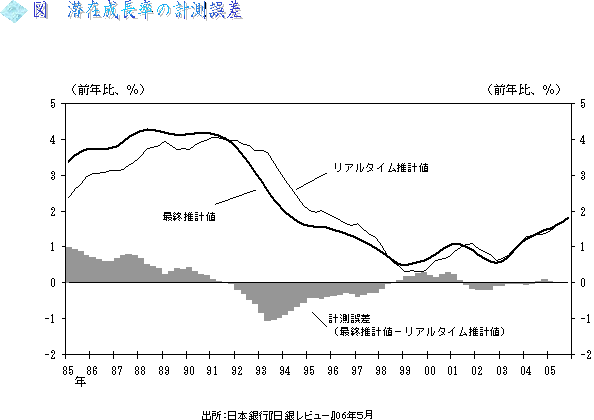
これは、鉱工業稼働率、労働力化率、パート比率などについて推計したトレンドを潜在成長率の推計に用いることから来る宿命である。現時点(06年)の潜在成長率の「リアルタイム推計値」では、04年までの稼働率や労働力化率の循環的低下がトレンドの推計値に下振れ誤差を生み、パート比率の循環的上昇がトレンドの推計値に上振れ誤差を生むため、将来推計可能となる06年の潜在成長率の「最終推計値」よりも低く出ている可能性が高いのである。
過去には一%の誤差があったことを考えれば、現時点で一%の需要超過は、まだ需給均衡かも知れない。仮に〇・五%の誤差としても、二%弱の潜在成長率は二%強となり、本年の四〜六月期(年率一・五%成長)と七〜九月期(同二・〇%)は需給ギャップが再拡大していることになる。今後需給面から物価が必ず上昇するとか、賃金上昇率が加速すると断定するのは、危ないのではないか。
実際、『展望レポート』で消費者物価(除く生鮮食品)上昇の要因分解を見ると、前年比の上昇は石油製品の上昇によるところが大きく、これが無かったり、下落に転じたりすれば、消費者物価の前年比が再びマイナスになるリスクがある。
関連してもう一つ下振れリスクを指摘すると、個人消費の見通しが楽観的に過ぎないか。『展望レポート』は国民負担の増加に全く触れていないが、増税や社会保険料引上げが目先06年度に2・6兆円(一世帯当たり5・3万円)、既に決っているだけで07年度についても、2・1兆円(同4・2万円)ある。ビジネスモデル転換という構造的要因の下で、緩やかにしか増えない雇用者報酬にとって相当な重荷ではないか。
最後に設備投資や土地投機の上振れ懸念として、『展望レポート』に実質金利の議論がないのが気になる。消費者物価上昇率から見て、実質コールレートはゼロないしマイナスだが、構わないのか。『短観』に表れた企業の「予想インフレ率」から見て、実質長期金利の水準をどう判断しているのか。マクロ経済はまだ需要超過になっていなくても、異常に低い実質金利の下で、地価上昇が加速するリスクはあるのではないか。日銀が新法の下で毅然たる政策を打つためにも、そうした情勢判断の確かさが問われる段階にある。