![]()
![]()
ポスト小泉に向けて
“「小泉経済政策」が残した課題”(『週刊エコノミスト』2006年9月12日号)
鈴木 淑夫(鈴木淑夫政経フォーラム代表、元日本銀行理事)
小泉純一郎政権が終わろうとしている。同政権下の日本経済を振り返り、その経済政策の本質と残された課題を考える。
2001年4月に小泉政権が発足した直後の日本経済は、惨憺たる有様であった。鉱工業生産は01年4〜11月の8か月間に15.4%急落し、実質GDP(国内総生産)は01年第2(4〜6月)〜第4(10〜12月)の3四半期連続のマイナス成長で、2.2%低下した(図1)。その後も回復は極めて緩やかであったため、企業倒産は激増し、完全失業率は03年1月に5.5%に達した。株価は03年4月に日経平均で7607円まで落込み、金融恐慌前夜の様相を呈した。同月のペイオフ解禁は2年間延期された。
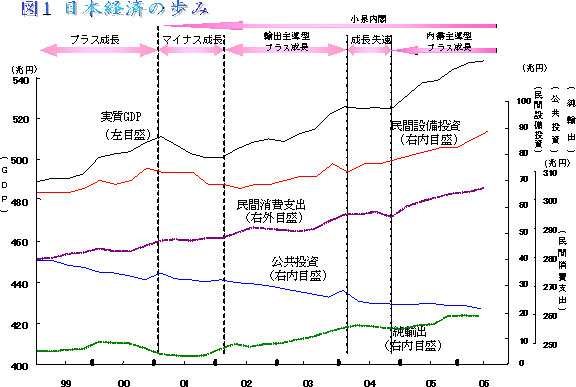
しかし、幸運にも小泉政権は、米国と中国の成長加速に伴い、02年第2四半期から04年第1四半期(1〜3月)まで、輸出と輸出関連設備投資に主導された緩やかなプラス成長に恵まれ、最悪期を脱する。その後、両国の成長減速に伴い純輸出(輸出総額−輸入総額)が減少すると成長は再び失速し、04年第2〜第4四半期にはマイナス成長に陥る。
回復をもたらしたのは「三つの過剰」の解消
内需関連も含む広範な設備投資と民間消費に主導された力強い回復が始まったのは、図1のように05年第1四半期からである。この内需主導型成長は、バブル崩壊後に表面化した企業の「三つの過剰」、すなわち設備(不動産を含む)、雇用、債務の過剰が、10年余りに及ぶ企業のビジネスモデル転換の努力によって遂に解消したことが、大きな要因となっている。
「三つの過剰」が続いた04年頃までは、企業(銀行を含む)の収益は、過剰な設備や営業所の除却、不動産の損切り売り、高齢正社員の慫慂退職、債務返済、不良債権処理などの後ろ向き資金に使われ、新規の設備投資や雇用など前向きにはあまり使われなかった。
その結果、第一に供給面では、その間の雇用と設備の効率が低下し、潜在成長率が下がった。
第二に需要面では、企業収益の回復が新規の設備投資と雇用の回復にあまり結び付かず、需要相互の波及効果が低下した。
第三にこのことは、需要喚起政策の有効性を低下させた。
第四に銀行は、自己資本を取り崩して不良債権の処理に投入し、同時に自己資本比率の低下を防いでBIS(国際決済銀行)規制を守るため、自己資本比率の分母となる貸し出しを減らすべく貸し渋り、貸しはがしに走った。これが量的緩和政策の信用拡張効果を無効にした。
「三つの過剰」は、05年に入る前後から後退し、解消して行った。日銀短観の「生産・営業用設備判断」と「雇用人員判断」の「過剰」超幅は急速に縮小し、「不足」超に転じた。法人企業統計の債務残高対売上比率は低下し、バブル末期の90年頃の水準に戻った。この結果、設備投資の回復は輸出関連のみならず、内需関連の製造業や非製造業へ広がり、加速し始めた。雇用は増加に転じ、完全失業率は4.2%(06年6月)に低下した。05年度の経済成長率はバブル崩壊後最高の3.2%に達し、日銀短観(大企業)と法人企業統計(全産業)の売上高経常利益率は、バブル期のピークを超えた。
頭にあるのは新古典派モデル?
以上のように、小泉政権下のマクロ経済は、当初危機的様相を呈しながらも、5年間の通計では、量的拡大を遂げた。00年度平均と05年度平均を比較すると、実質GDPは7.7%成長し、鉱工業生産は2.2%上昇し、失業率は4.7%から4.4%へ低下した。5年間の成果にしては小さいが、06年度も拡大を続けているので、最終的にはもう少し大きくなるだろう。
しかし、興味深いことに、物価、賃金などの価格指標は、この5年間に低下しているのである。同じように00年度平均と05年度平均を比較すると、全国消費者物価(生鮮食品を除く)は1.9%下落、名目賃金(現金給与総額)は5.2%低下、雇用者報酬は4.2%の減少である。
小泉政権下のマクロ経済パフォーマンスの特色が、量的指標の拡大と価格指標の低下であったということは、小泉政権の経済政策を評価する上で、単にデフレ経済と言う以上に重要な手懸りを与えてくれる。
よく知られているように、価格・賃金の下方硬直性を前提としたケインズ派の不均衡モデルでは、財政刺激や輸出伸長などの外生的な需要ショックを与えない限り、量的拡大は実現しない。これに対して、価格・賃金の伸縮性を前提とする新古典派の均衡モデルでは、需要ショックを与えなくても、価格・賃金の下落によって民間市場経済は自律的に拡大して均衡を回復する。
小泉政権は当初の危機的局面においても、財政拡張政策を用いなかった。政府の一般会計歳出予算は、公共投資削減(図1)を中心に5年間減り続け、通計で8.0%減少した。需要ショックは、もっぱら輸出増加頼みであった。
それにも拘らず、経済は量的拡大を遂げた。当初の危機的状況の下でマクロ需給バランスが悪化すると、価格と賃金が市場競争を通じて伸縮的に低下したからである。小泉政権下の日本経済は、新古典派モデルの世界に近かったのだ。
小泉政権は日本経済のその特性を承知の上で、財政拡張政策を発動せず、市場原理主義に基づく米国流の「新自由主義」政策を実行したのであろうか。毎年、米国政府が日本政府に突きつける『年次改革要望書』の中身が郵政民営化や不良債権早期処理など、かなり小泉政策に反映されていることや、同政権下で経済財政政策担当相、金融相、総務相を歴任した竹中平蔵大臣が当初頻繁に米国を訪れ、政府や学界と意見交換していたことから判断すると、少なくとも竹中大臣の頭の中には新古典派モデルと新自由主義経済政策があったのかも知れない。
しかし以下に見るように、小泉政権が実際に行った政策には、本来の「新自由主義」政策とは言い切れない面が少なくない。
前例のない政府債務増大
まず財政政策である。公共投資は確かに削減したが、当初の危機的状況の下で01年度〜03年度まで税収が4兆円落込んだので、この3年間に財政赤字は拡大し、国債発行額は28.3兆円(01年度当初予算)から36.4兆円(03年度決算)に拡大した。その後は経済の量的拡大に伴って自然増収が始まり、06年度当初予算の国債発行は政権発足時の公約通り30兆円に収まったが、5年間の国債増発の累積により、政府債務残高は538兆円(00年度末)から827兆円(05年度末)へ289兆円(54%)も増加した。「借金王」と自嘲した小渕首相を上回る大記録である。
その結果、図2に示したように、政府債務残高の対GDP比率は急上昇し、160%と米国やユーロ地域の約2倍に達した。
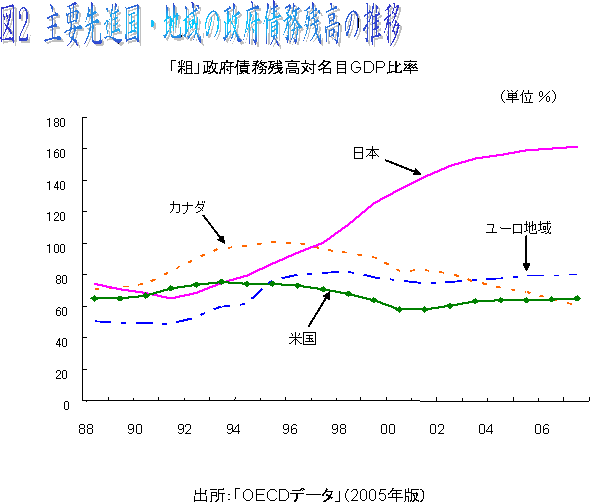
このような赤字国債大増発を伴う財政支出は、ケインズ経済学的思考では「景気の自動安定化装置」であり、経済の拡大に寄与している。国民が赤字国債の増発分だけ将来は増税があると考えるならば、拡張効果は生じないが(リカードの公債中立命題)、全ての国民がこのような「合理的期待」をもっているとは考えにくい。ある程度の「財政錯覚」があるとすれば、小泉財政政策は拡張的効果を持ち、新自由主義の政策とは異なっている。本来の新自由主義は、財政政策や金融政策が経済成長を需要面から促進するとは考えていない。財政政策の目標は、構造改革によって効率を高め、供給面から成長を促進することである。
では、小泉政権の構造改革は、日本経済の効率を高めたのであろうか。官から民へ、国から地方へ、そして小さな政府を実現すると小泉首相は言い続けてきたが、本当にそうなったのか。道路関係4公団を民営化したが、高速道路建設は当初予定通りである。郵政民営化は、巨大な銀行、生保、郵便会社を生み出して、これ迄以上に民業を圧迫しようとしている。国が使途を決める権限を残したまま、補助金の削減や交付金化が図られ、地方が自由に使える交付税はむしろ減っている。民間や地方のビジネス・チャンスを拡大し、国は小さくなるという本来の新自由主義政策は進んでいない。
経済効率を高める上で一定の成果を挙げたのは、「規制改革・民間開放推進会議」の規制撤廃である。しかし、これも金融などではある程度進んだが、医療、教育・福祉、農業では所管省庁と既得権益の壁にぶつかり、多くの重要分野で立ち往生している。今後期待されるのは、公共の仕事に競争を導入する「市場化テスト(官民競争入札)」であるが、これで官から民へ仕事が移るのか、まだ分からない。
では、民需主導型成長を実現した「三つの過剰」解消と小泉政権は、どう係わっていたのか。設備と雇用の過剰を解消し、バブル期を上回る収益率を挙げているビジネスモデルの転換は、価格・賃金の伸縮性を生かした企業の自助努力によるもので、小泉改革のお陰ではない。
小泉政権が積極的に係ったのは、不良債権の早期処理である。02年10月の「金融再生プログラム」により、不良債権を厳しく査定し直した上、05年3月までにその半減を目指し、早期処理を促した。その過程で債務超過に陥った銀行は整理し、自己資本比率規制を守れなくなった銀行には公的資本を注入した。不良債権の相手側である企業は、時価会計と減損会計を適用して厳しく査定され、多くの中小企業が「債権回収機構」送りとなった。
この原則が貫かれれば、「りそな銀行」も03年春に整理される運命にあった。当時、株価は金融恐慌の不安に怯え、日経平均で7607円まで下がり、それが金融機関や基金の評価損を拡大し、更なる金融不安の種となった。ここで小泉政権は「too
big to fail(大き過ぎて潰せない)」政策に転じ、債務超過のりそな銀行に資本の3分の2に相当する公的資本を注入して事実上国有化し、救済した。潰れて行った中小銀行やその取引先から見れば極めて不公平な政策であるが、これが金融恐慌を防いだ。日本から逃避していた海外投資家が戻り、株価が底入れしたからである。
歳出内容の転換が必要
これは小泉政権の一応のサクセス・ストーリーであるが、後に残された課題は少なくない。
まず何よりも膨大な政府債務である。政府債務残高対GDP比率がさらに上昇して行くと、予算に占める国債費の比重が高まり、政策経費を圧迫するので、政府の政策遂行能力が低下する。この比率を下げるには、財政のプライマリー・バランス(国債費を除く歳出と税収の収支)を黒字化しなければならない。そのため今後5年間で、まず11.4〜14.3兆円の歳出を削減し、次に2〜5兆円の歳入増加を図る中期計画が決まった。
しかし、公共事業費、人件費、社会保障費、地方交付税の理念なき一律削減では構造改革にならない。官から民へ、国から地方への機会移転という理念に基づく削減でなければ、経済を供給面から効率化するどころか、むしろ潜在成長率を落として赤字拡大要因になり兼ねない。
民間の市場競争原理に信を置く新自由主義は、同時に事前的ルールの明確化と事後的看視の強化を伴わなければ、不公平と不安が拡がる。ライブドアと村上ファンドの不正、耐震設計偽装、鉄道や航空機の事故、流水プール事故、アスベスト汚染、暖房器具や湯沸かし期の欠陥など相次ぐ事件は、競争促進ばかりで事後的看視が不十分であったことを示唆している。しかし、事後的看視の強化は歳出増加を伴う。これを歳出削減の要請とどう調和させるか。
新自由主義の競争促進はまた、勝ち組と負け組、企業と家計、正社員と非正社員、中央と地方などの格差拡大をもたらしている。これを補うセイフティーネットの強化もまた、歳出増加を伴う。
このように、公正と安全を保障する歳出増加は、財政赤字縮小と矛盾するが、それを実施しなければ、市場原理に基づく効率を安心して追及し、持続的成長を維持することが出来なくなる。そうなれば税収が落ちて、財政赤字の縮小も難しくなる。ポスト小泉には明確な問題点の整理と、メリハリの効いた歳出内容の転換が求められている。