![]()
![]()
政府与党内の金利・成長率論争は不毛:根拠薄弱な財政再建議論の前提(『週刊東洋経済』2006年4月22日号「論点」)
要点
●金利と成長率の関係は理論的にも実証的にも簡単に断言できない。
●財政再建のためには高い実質成長率と低インフレ率を目指すべき。
●それを実現するために大切なのは、財政支出削減の中身と金融政策。
財政再建の中期シナリオを議論した3月16日の経済財政諮問会議では、民間委員と与謝野馨経済財政大臣、谷垣禎一財務大臣らが主張する4%の長期国債金利と3%の名目成長率という前提と、逆に3%の長期国債金利と4%の名目成長率という竹中平蔵総務大臣、中川秀直自民党政調会長らが主張する前提が対立した。
【両派の対立は根拠薄弱】
よく知られているように(ドーマー条件)、中期的に長期国債金利が名目成長率を上回っていると、プライマリーバランス(公債の償還・利払い費を除いた政府の一般歳出等と税収との差、以下PB)を均衡させても、政府債務残高の対GDP比率は低下しない。低下させるためにはPBの大幅黒字化という厳しい財政再建が必要である。これに対して、中期的に長期国債金利が名目成長率を下回っていると、PBを均衛させることによって、政府債務残高対GDP比率は低下していく。
したがってこの対立は、厳しい財政再建シナリオ(財務省型)と、もう少し緩やかでも再建できるというシナリオの対立である。
民間委員(学者)の中には、「理論的にいって先進国では国債金利は名目成長率より高い」といって前者を支持する人がいる。逆に同じ学者の竹中大臣は「日本では戦後金利のほうが成長率より低かった」と主張している。しかし、金利と成長率の関係は、理論的にも実証的にも、それほど簡単に断言できる話ではない。
米国の元財務次官サマーズの実証研究によると、主要先進国では「資本収益率が成長率を上回っている(動学的効率性が満たされている、すなわち資本に対する選好が強い)」という結果が出ている。民間委員(学者)は、この資本収益率を長期国債金利と置き換え、「先進国では国債金利が成長率を上回る」といっているのではないか。
しかしここでいう資本収益率とは、民間企業の発行する長期社債の利回りや株式のROE(資本収益率)のことである。図1を見ればわかるように、財政再建に係わる長期国債の利回りは、リスク・プレミアム分だけ民間の長期社債の利回りよりも低い(図1では最大1%、平均0.5%の差)。したがって、サマーズの実証研究から「先進国では国債金利のほうが成長率より高い」とはいえないのである。
では、竹中大臣のように、「日本では戦後、金利のほうが成長率よりも低かった」といって、今後の中期シナリオの国債金利を名目成長率よりも低くするのは正しいのであろうか。人為的低金利政策で金利が低く規制され、他方、高度成長とインフレで名目成長率が好況期には10%台であった70年代までの日本では、そのとおりである。しかし、以後は金利が自由化されて長期国債の市場利回りは時に10%を超え、他方では高度成長の終焉と物価の安定で名目成長率が落ち込んだので、図1に見られるように一概に長期国債金利が名目成長率を下回っていたとはいえず、逆の年のほうが多い
実は、OECD加盟国全体を見ると、1980年までは国債金利が名目成長率を下回っていた国のほうが多かったが、その後99年までは逆に国債金利が成長率を上回った国のほうが多くなった。しかし、2000年代に入ると、比較的好況な00年、04年、05年には、再び国債金利を成長率が上回っている国が多い。
日本でも図1に明らかなように、長期停滞の下で国債金利が名目成長率を上回っているが、停滞に陥る前の87〜90年度や民需主導の本格的回復が始まった05年度(推計)には成長率が国債金利を上回った。
以上のように、金利が成長率より高いとする与謝野・谷垣派も、逆だとする竹中・中川派も、理論的、実証的な根拠は弱いのである。
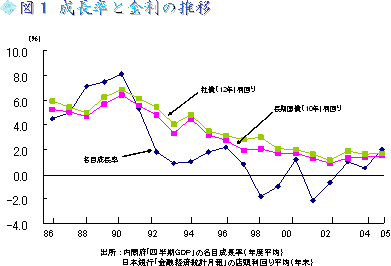
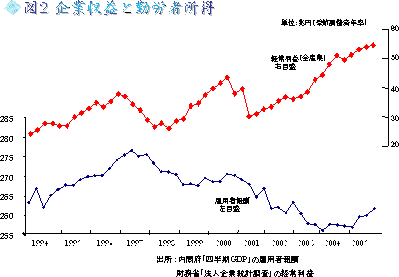
【高成長・低インフレは可能】
前述したOECD加盟国の歴史的傾向に示されているように、民間主導で比較的高い実質成長を続けている時期には、財政主導で何とか成長を維持している時期よりも、名目成長率が金利を上回る例が多い。またアレシナの研究によると、財政再建成功国では成長率が上昇し金利が低下すること、逆に財政再建失敗国では成長率が低下し、金利が上昇することが示されている。財政再建成功国を民需主導型成長、失敗国を財政主導型成長と置き換えれば、同じ事実を物語っているといえよう。
また、インフレ目標値採用国と非採用国を比較すると、採用国のほうがドーマー条件の改善が大きいという報告がある(本誌06年2月25日号論点を参照)。これはインフレ目標値を採用してインフレ率の引き下げに成功した国は、そうでない国よりも名目成長率が金利を上回る傾向が強いということであろう。
新聞報道によれば、名目成長率の内訳は与謝野・谷垣派が実質成長率1%台後半、インフレ率1%台前半、竹中・中川派が実質成長率もインフレ率も2%となっている。つまり実質成長率もインフレ率も、後者のほうが前者よりも高いのである。
したがって実質成長率が高いことに着目すれば、竹中・中川派のほうが名目成長率が国債金利を上回る可能性が高い。しかし、インフレ率が低いことに着目すれば、与謝野・谷垣派のほうがそうなる可能性が高い。それなのに、国債金利を名目成長率3%よりも高い4%と置き、自らドーマー条件を満たせないとしている。
両派を比較すると、実質成長率が高くなればインフレ率が高くなるという関係がみられるが、これは短期の関係である。中長期的にはフィリップス曲線(賃金上昇率と失業率の関係、インフレ率と実質成長率の関係をも示す)は垂直であり、実質成長率とインフレ率に一義的な関係はない。財政再建の中期シナリオを議論するときに、実質成長率が高くなればインフレ率も高くなると考えるのは誤りである。
インフレ率の高さを決めるのは、基本的には金融政策である。他方、中期的な実質成長率を決めるのは、全要素生産性と資本ストックと労働力の増加率に働きかけるさまざまな構造政策である。歳出と国民負担の中身と伸び率を決める財政政策(中期財政再建策)も、その一つである。
金利が名目成長率を下回る状態を中期的に保って財政再建を成功させるには、実質成長率を高め、インフレ率を低めて1%前後に安定させる政策を探らなければならない。金利が予想インフレ率を反映していること(フィッシャー効果・名目金利=実質金利+予想インフレ率)を考えれば、金融政策は予想インフレ率を1%前後に安定させる政策に徹して、長期金利を低めに保つべきである。
中期的な金融政策の一つとして、ゼロ金利を出来るかぎり長く保つべしという「長期金融緩和論」が、政府・与党内にあるとすれば、誤りである。ゼロ金利の持続で高成長と低金利が続くのは、インフレやバブルが発生しない間の短期シナリオである。中期的には必ずインフレかバブルか、あるいはその両方が発生し、金利上昇と反動不況が起きる。結果は高金利と低成長になる。87年以降の経験をまさか忘れたわけではあるまい。日本銀行はゼロ金利の早まった解除をしてはならないが、かといって、インフレやバブルの芽を早目に摘むための緩やかな利上げの開始を遅らせてはならない。
財政再建をやりやすくする高い実質成長の鍵は、実は財政再建のやり方自身の中にある。与謝野・谷垣派に近い民間委員(学者)の一人がある所で講演し、「財政再建には歳出削減と国民負担の増加の二つしか道はないが、二つとも成長抑制的に働く。ゆえに高い実質成長率を前提とする中期シナリオは描けない」と述べた。
この考え方は間違っている。歳出削減が、①民間や地方自治体への過剰介入行政の廃止と担当組織・人員の削減、②民間に移譲できる仕事をしている特別会計、特殊法人、公益法人、独立行政法人などの廃止、によって実現するのであれば、民間と地方のビジネスチャンスが拡大し、経済全体の効率は高まるので、実質成長率は上昇するであろう。
政府・与党が今国会で成立させようとしている行政改革推進法が、このような歳出削減に本当に寄与出来るのか、国民は注視していかなければならない。
【持続的成長を実現するには】
今回の景気上昇は、02年3月から始まったとされているが、実は04年第1四半期までの輸出主導型成長(純輸出の成長寄与率41%)、04年第2〜4四半期の失速(通計マイナス0.3%成長)、05年第1四半期から始まった内需主導型成長(内需の成長寄与率83%)の三つから成っており、皆性格が違う。
純輸出と輸出関連設備投資にリードされた最初の回復期は、図2に示したように、輸出企業を中心に企業収益が回復しても、雇用者報酬(雇用と賃金)は減り続けていた。これは改善した収益が三つの過剰解消(債務返済、雇用整理、設備除却)に使われ、雇用と賃金(雇用者報酬)の回復や新規設備投資にあまり向かわなかったからである。このため、輸出回復↓雇用・賃金・新規設備投資の回復↓内需回復↓雇用等の一層の回復、という好循環が始動せず、輸出回復が内需主導型回復に点火するメカニズムが壊れていた。
それが典型的に現れたのが、04年第2〜4四半期の成長失速である。米国と中国の成長減速で輸出が鈍ると、景気全体が失速し、3四半期通計でマイナス成長となった。しかし、05年に入ると、図2に明らかなように、雇用者報酬が上昇に転じた。設備投資の回復も輸出関連製造業から内需関連の製造業と非製造業に広がり始め、全体として加速してきた。民間消費と設備投資という二本柱に支えられた内需主導型成長に遂に点火したのである。
05年から始まったこの成長は、それ以前とは別の型の成長が新しく始まったと考えるべきである。二つを区別するキーワードは、「三つの過剰」だ。三つの過剰は04年まで四つの面から成長を制約していた。
第一に供給面では、過剰な設備と雇用が経済の効率を低下させ、全要素生産性の上昇率を引き下げて潜在成長率を低下させた。第二に需要面では、過剰な設備と雇用が設備投資と新規雇用(したがって勤労所得と個人消費の増加)を抑え、国内民間需要の増加率を引き下げた。
第三に企業は、収益の回復を過剰設備の除却、不要不動産の損切り売り、過大債務の返済に振り向け、前向きの新規設備投資や雇用増加に使わなかったため、拡張的財政政策の乗数効果が小さくなり、政策の有効性が低下した。弟四に銀行は、収益と自己資本を不良債権の処理に投入し、同時にBIS規制上の自己資本比率と収益性を出来る限り維持しようとしたため、貸し渋り、貸しはがしに走り、金融政策(ゼロ金利、量的緩和)の有効性を著しく低下させた。
この四つの条件が消えて始まった05年以降の回復は、まだ「若い景気」である。三つの過剰が解消したばかりなので、設備投資も雇用も賃金も借り入れもストック面などから見て、数年間伸び続ける条件を持っている。GDPベースの需給ギャップにも余裕がある。
金融政策が弾力的に運営されて1%前後のインフレ率を維持し、財政再建が民間と地方を活性化する歳出削減を中心に行われるならば、05年から始まった成長は中期的に持続し、高い実質成長率と低いインフレ率によってドーマー条件が満たされ、日本の財政再建は成功するに違いない。大切なのは財政支出削減の中身であり、成長率と金利のどちらが高いかを議論している政府与党内の論争は不毛である。