![]()
日本銀行の次なる課題:量的緩和を解除し自縄自縛状態を解け(『週刊東洋経済』2005年7月30日号「論点」)
要点
●日銀の量的緩和は長期金利上昇を防いだが、デフレ脱出には効果なし。
●秋以降に消費者物価はゼロ%以上になる兆し。政策転換の条件整う。
●日銀当座預金残高目標を引き下げ、次なる政策課題に備えよ。
【量的緩和、新機軸の功罪】
2001年3月に量的緩和政策に踏み切ったとき、日本銀行は二つの新機軸を打ち出した。
第一は金融政策の操作目標を、従来のコールレートから日銀当座預金残高に変え、目標残高を所要準備預金4兆円(現在は6兆円弱)を上回る5兆円としたことである。1兆円の余剰資金が在るので、コールレートは当然ゼロ金利に張り付いたままになる。そこで一層の金融緩和を目標残高の引上げで進めることとし、長期国債の買オペを増やすなどの手段によって、04年1月までの間に目標残高を9回引上げ、現在は30〜35兆円の巨額に達している。
新機軸の第二は、この量的緩和政策を「全国消費者物価(生鮮食品を除く、以下同じ)の前年比上昇率が安定的にゼロ%以上となるまで継続する」と市場に約束したことである。
第一の日銀当座預金の積上げによって、ベースマネー平残の前年比増加率は01年7.4%、02年25.7%、03年16.4%、04年7.1%と著しく伸びたが、この4年間のマネーサプライ(M2+CD)平残の前年比増加率は1.7〜3.3%にとどまった。これに先立つ4年間(量的緩和政策なし)の2.1〜4.0%よりも逆に低い。消費者物価のデフレも続いた(第1図)。
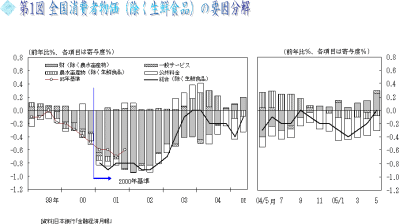
日銀当座預金の積み増しは、市場に不活動残高を積み上げただけで、銀行貸出を刺激することは出来なかった。不良債権早期処理、自己資本比率維持、収益改善の三重苦の下で、銀行は新規貸出に慎重になり、古い貸出の回収を急いだからだ。
巨額の不活動残高の存在は、万が一金融システムが動揺した場合に備える事前の安心材料として、唯一の意味を持った。これが第一の新機軸のたった一つの功績と言えよう。
第二の新機軸は、コールレートのゼロ金利が続く時間軸を、消費者物価という客観的指標で示すことにより、市場が予想する将来のゼロ金利の継続期間を安定させる効果を持った。現在の長期金利は、将来の予想短期金利の加重平均にリスク・プレミアムを加えたものであるから、この時間軸効果によって、ゼロ金利政策解除の誤った思惑によって長期金利が上昇することを防ぎ、またリスク・プレミアムを小さくして長期金利を引下げることに成功した。
これによって、企業投資や住宅投資を下支える上で、何がしかの効果があったかも知れない。また財政の金利負担軽減の効果も大きかった。
以上の効果に対し、新機軸の最大の副作用は、金融機関経営の自主性喪失と市場の歪みである。金融機関経営とは、将来の金利、資金のアベイラビリティ、顧客の信用などについて、自主的に判断してリスクをとり、ポートフォリオを調整していくものだ。しかし量的緩和政策の下で、日本銀行が巨額の長期国債の買オペによって大量の長期資金を安定した金利で供給し続けた結果、金融機関は市場との自主的な対話で将来の金利や資金事情を予想し、リスクを取る必要が無くなった。
この日銀オペに対する過度の依存は、確実な日銀オペが不確実な市場に代替していることを意味する。いつ金融システム不安が発生するか分からない非常時なら仕方のない事であるが、その時期を過ぎた今日、金融機関の自主性喪失と市場機能麻痺のデメリットは大きい。
【秋以降デフレ脱却の条件】
金融機関は自ら金利や資金ポジションを予想しつつポートフォリオを調整する意欲と能力を失い、預金吸収に何の魅力も感じなくなっている。コール市場の規模は縮小し、本来の機能が働かなくなっている。
このような状態はいつ迄続くのか。「消費者物価の前年比が安定的にゼロ%以上」になる迄量的緩和政策を続けると約束した以上、新機軸の副作用が大きくなったからと言って政策転換すれば、日銀に対する信頼感が失われる。一度失えば、以後「市場の期待」に働きかける日銀の発言は全部信用されなくなるであろう。そのコストは大き過ぎる。
そこで問題は、いつになったら消費者物価が上昇するかである。消費者物価の直近の計数は五月であるが、これが前年比ゼロ%になった。
第2図に明らかなように、国内の企業物価指数は、中国における基礎資材のボトルネック・インフレや世界的な原油価格の高騰によって、昨年4〜6月期から前年を上回っている。これに対して消費者物価は、99年7〜9月期や03年10〜12月期、04年1〜3月期などに一時的に前年比がゼロ%となることはあっても、傾向としては前年を下回り続けている。本年5月のゼロ%は、ガソリン価格の高騰が主因であるが、前年6月にもガソリン価格が上昇しているので、本年6月以降もゼロ%以上を続けるとは限らない。
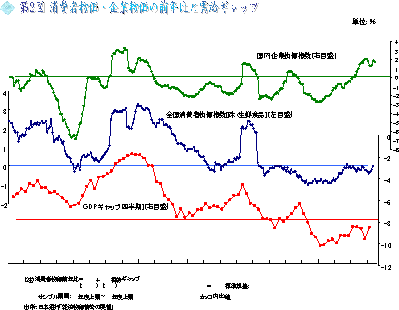
企業の段階で物価が上昇しているのに、何故消費者物価は上昇しないのであろうか。
第1図に明らかなように、昨年9月以前の前年比マイナス幅に一番大きく寄与していたのは財(除く農水畜産物)の値下がりであったが、その後現在までは、企業物価の上昇を反映して消費者物価中の財(同)の価格も上昇している。代って消費者物価の足を引張り、前年比をマイナスにしているのは、公共料金と農水畜産物(除く生鮮食品)の下落である。公共料金では、昨年11月と本年1月の通信料金引下げが、消費者物価全体の前年比を0.1%ずつ引下げた。農水畜産物(同)では、昨年10月の米価値下がりが、消費者物価全体を0.2%引下げた。
この二つの効果を合わせた合計0.4%が前年比マイナス幅から消えるのは、本年10月から明年1月の間である。現在の消費者物価前年比がゼロ%であることを考えると、たとえ6月に再びマイナスになったとしても、10月以降にプラスに転じる可能性は十分考えられる。
このような個別価格の動きを全体として平均したのが物価指数であるが、それを大きく左右するのは日本経済全体のマクロの需給事情である。マクロの需給逼迫が無いのに個別価格の事情で物価が上昇すれば、実質購買力が減少してマクロの需要は減り、マクロの需給緩和で物価は反落する。その逆もまた真である。
第2図には日本銀行が推計したGDPベースの需給ギャップを描いてあるが、これと消費者物価の前年比は、かなり似た動きをしている。第2図の(注)に示した回帰式によれば、需給ギャップがマイナス7.8%の時に消費者物価の前年比がゼロ%になる。本年1〜3月の需給ギャップはマイナス8.5%なので、あと0.7%以上縮めば消費者物価がゼロ%以上になり、量的緩和政策解除の条件が整う計算になる。
この回帰式の決定係数と誤差を考慮すると厳密なことは言えないが、本年度の成長率が01年度(マイナス1.1%)や02年度(0.8%)のように低ければ無理であるが、03年度(2.0%)や04年度(1.9%)並みであれば、需給ギャップ面からもデフレ脱出の条件が出てくるという程度のことは言えよう。
【量的緩和解除の道筋】
このような展望に立って、今後の在るべき金融政策を考えてみよう。
まず、操作目標である日銀預金残高の引下げに着手すべきである。本年5月、日本銀行政策委員会は、日銀当座預金が操作目標である30〜35兆円の下限を一時的に下回ることを容認する決定を下し、6月に入ると、当座預金残高が29兆円台に低下するのを2日間放置した。同じことは、7月中にも起きるであろう。
買オペの札割れが生じ、日銀当座預金が目標残高を下回るようになったのは、金融システム不安の後退で、予備的動機に基づくベースマネー需要が落ちているからである。前述した第一の新機軸の効果が、意味を失ってきたのだ。そうなると、第一の新機軸の副作用、即ち金融機関経営の自主性喪失と市場機能の歪みだけが残る。日本銀行は副作用を小さくするため、予備的動機が後退した分だけ目標残高を引下げるべきである。取引動機や資産動機に基づくベースマネー需要は今まで通り潤沢に満たされるので引締め転換ではなく、勿論ゼロ金利と時間軸効果は続く。それを日本銀行は強調すべきだ。
日本銀行は目標残高を9回引上げる際、金融緩和の効果が進むと説明したが、実際にはマネーサプライの増加率は増えず、長期金利は低下せず、デフレも改まらなかった。目標残高を引上げて効果が無かった以上、引下げても影響は出ない。それなのに、金融引締めと誤解されるのを恐れ引下げをためらっている。この自縄自縛は、勇気を持って解かねばならない。
目標残高を引下げても、所要準備の6兆円弱に近づくまで、ゼロ金利は保たれる。反面、次のステップに備えた金融政策の機動力回復、金融機関経営の自主性回復、市場機能の復活の準備は整う。日銀当座預金残高を所要準備スレスレとし、操作目標をプラスのコールレートに戻す時期は、消費者物価と背後の景気動向次第である。早ければ、本年10月〜明年1月の間に、消費者物価の前年比がゼロ%を上回るようになるであろう。それが継続的かどうかの判断は、景気の展望に懸かる。
6月調査「日銀短観」によると、本年度はスピードが落ちるものの増収増益が続き、高い企業収益率が維持される。成長を支える要因は、雇用の緩やかな回復を背景とする個人消費、および設備投資である。雇用も設備投資も従来の輸出関連製造業から対個人サービス非製造業にウェイトが移っている。最近の常用雇用者の動きを見ても、前年に比べて大きく増えているのは医療・福祉、情報通信、複合サービス、教育学習支援、サービス(合計1498万人)で、製造業(861万人)ではない。
輸出関連製造業に主導された景気回復は昨年下期に失速したが、本年1〜3月期の4.9%成長は、対個人サービス非製造業を中心とした個人消費と設備投資で実現した。4〜6月期以降もこの傾向が続いて需給ギャップが縮小すれば、秋以降来年上期にかけてデフレが解消し、政策転換の条件が整う。製造業は下期輸出回復に期待しているが、原油高騰や米中の成長減速で裏切られると、需給ギャップの予想は下振れする。
日本銀行は目標残高の圧縮を進め、いつでも量的緩和・ゼロ金利政策から転換できる態勢を整えながら、下期以降の経済動向を注意深く見守っていく必要がある。