![]()
世界経済の現状と日本:雨宮日銀理事との討論(10/13昼食勉強会)を踏まえて(H22.10.22)
―円高対策とデフレ対策は「対策」の意味が違う―
【円高対策は円高順応策、デフレ対策はデフレ克服策】
現在、日本経済が直面している大きな問題に、円高とデフレがある。それぞれについて円高対策、デフレ対策が議論されている。
しかし、同じ「対策」という言葉が使われていても、円高対策とデフレ対策では、その意味が違うことに注意すべきであろう。
円高対策は、円高を止めて、円安に戻す対策ではない。円高に日本経済をいかに適応させるか、あるいは円高をいかに活用するか、という対策である。
何故なら円高は止められないからだ。為替管理を撤廃し、自由な為替変動相場制をとっている以上、グローバルにつながった世界の為替市場の需給で決まる円相場の水準を、日本の市場介入という小さな売買で動かすことは、一時的には出来ても、長期的には不可能である。
これに対してデフレ対策は、デフレに順応する対策ではなく、デフレを止める対策である。何故なら、デフレは基本的には日本経済の需給で決まる現象だからである。デフレは日本のマクロ経済政策で止められる筈だ。
【米欧は不動産バブル崩壊とユーロ高バブル崩壊の調整過程】
この二つの「対策」の意味が違うことを理解せず、デフレ対策同様、円高を無くすことが円高対策だと思い込んで議論すると、話は混乱する。例えば、円高を直さない限り、株安も直らないという論理がまかり通り、株価悲観論、ひいては日本経済の先行き悲観論に陥ってしまう。
現在世界経済で起こっていることを大きく整理してみると、米欧先進国では07年以降に顕在化した不動産バブルの崩壊に伴うバランス・シート調整が進んでおり、それがリーマン・ショックを典型とする突発性金融危機を起こし、また米欧の経済成長を慢性的に停滞させている。
また、ユーロ・システム加盟国では、2007年までのユーロ高バブル(例えば一時は1ユーロ=160円台後半)に乗じて大量に起債した国債の償還負担が、ユーロ・バブルの崩壊に伴って増大し、財政緊縮を余儀なくされ、景気が停滞している。その中でギリシャ危機が発生し、アイルランド、ポルトガル、スペインなどの財政状況と景気も深刻化している。
【新興国・途上国は景気過熱の予防が課題】
他方、アジアを中心とする新興国・途上国では、産業化とインフラ整備に伴う高成長が続いており、課題は先進国とは逆に、いかにして景気過熱を防ぎ、高成長を長引かせるかにある。今週初めの中国における利上げは、その意味で適切であり、短期的には株価下落要因になっても、長期的には新興国・途上国、ひいては世界の成長を持続させる好材料として、評価されるであろう。
以上にように、世界経済の現状は、米欧先進国経済がバブルの崩壊に伴う調整が長引き、回復が遅れる見通しとなっているのに対し、新興国・途上国経済は景気過熱が危ぶまれる程の勢いで成長を続けている。
【世界経済成長の7割強は新興国・途上国が牽引】
IMFの見通しによると、下表の通り、2010〜11年の世界経済の成長率+4.5%に対する寄与率は、新興国・途上国が72%(うちアジアの新興国・途上国は48%)に達し、1990年代まで過半を占めていた先進国の寄与率は28%に落ちると推計されている。
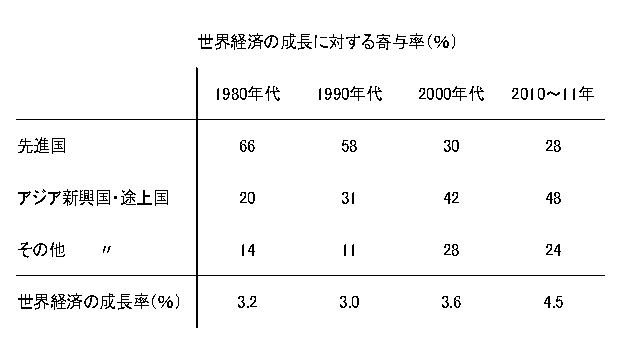
【日本にはバランス・シート調整はなく、高水準の不活動流動性がある】
このような世界経済の現状の中で、日本は特殊な立場に立っている。
日本は不動産バブルの崩壊に伴うバランス・シート不況を1990年代から2000年代初めにかけて経験し、現在は、米欧先進国とは異なり、バランス・シート調整の課題は残っていない。むしろ企業部門のバランス・シートには200兆円を超える現金・預金があり、家計部門のバランス・シートは1000兆円を超える資産超過がある。金融部門の不良債権比率もいまは低い。
このように、バランス・シート調整の重荷を背負っていない日本の通貨「円」が、不動産バブル崩壊やユーロ高バブル崩壊の調整が長引き、成長率が停滞している米欧の通貨、「ドル」と「ユーロ」に対して、相対的に強くなるのは市場の論理からいって当然の動きである。これを阻止しようと考える「円高対策」は、「天に唾する」類のことである。
【本年は先進国中日本の成長率は一番高く、円高基調は崩れにくい】
IMFの本年10月時点の世界経済見通しによると、2010年の成長率予測は、日本の+2.7%に対し、米国は+2.6%、ユーロ圏は+1.7%である。先進国の中では日本の成長率が一番高い。
日本の本年1〜6月の実質GDPの平均は、既に前年1〜12月の平均に対し+2.7%の水準である。従って、IMFの予測は、本年後半、即ち本年7〜12月をゼロ成長と見ていることになる。しかし、世界経済の下期成長停滞に伴う輸出の鈍化や、政策効果息切れに伴う消費の下期停滞を考慮しても、7〜12月のゼロ成長は弱過ぎる見通しではないか。恐らくプラス成長となり、2010暦年の成長率も+2.7%を上回り、もっとはっきりと米欧の成長率を上回るのではないか。
それが誰の目にも見えてくると、対ドル・ユーロに対する円高の基調は変わらない蓋然性が高い。
【新成長戦略産業の育成が不可欠の課題】
もともと1ドル=80円に接近している現在の円相場は、日本銀行が試算している円の実質実効為替レートでみると、1990年以降20年間の平均をまだ僅かに下回る円安水準である。従って、これによって今後の日本の成長に致命的な制約が加わるとは見られない。
企業は、2004〜07年の円安は「円安バブル」であり、現在の水準こそが正常である、と考えて経営すべきである。現在は、円高(実は円安バブルの崩壊)を活用して、海外の資源や優良企業を買収し、グローバルな経営戦略を展開する好機である。これに伴い、製造業を中心に企業の海外シフトが起きるのは、当然の成り行きである。
これは日本国内の雇用機会喪失を招くので、これを埋める新しい産業を、戦略的に発展させなければならない。これが新成長戦略産業である。
情報通信、新エネルギー、環境、IT、バイオ、医療、介護、教育、育児などの分野である。
政府は、これら新成長戦略産業の発展支援に力を注いでおり、日本銀行も「成長基盤強化を支援するための資金供給」によって、民間金融機関向けのこれら産業に対する融資を低利(現在は0.1%)でリファイナンスしている。
【金融の量的緩和だけでは需給ギャップは縮まらない】
しかし、これらの政策効果が出てくるのはこれからである。それ迄は、現在のマクロ需給ギャップが急速に縮むとは思われないので、デフレは持続するであろう。逆に言うと、新成長戦略産業を発展させて成長率を高め、マクロ需給ギャップを縮めることこそが、デフレ対策の基本である。
これに関連して、「インフレ・ターゲット」を掲げて、デフレ・ギャップと同じ大きさの資金供給を金融政策が実施すれば、デフレ・ギャップは解消してマイルド(1〜3%)のインフレに変わると主張する人達がいる。
しかし、これは理論的にも実証的にも誤りである。理論的には、中央銀行の通貨(または資金)供給量の一定割合が総需要の増加に結び付く保証がない(通貨需要関数の不安定化)。実証的には、リーマン・ショック後、米欧先進国は果敢な量的緩和を実施してきたが、インフレ率は逆に低下している。
【日本のデフレは需給ギャップだけでは説明がつかない】
デフレの一つの原因がマクロ需給ギャップの拡大にあり、マクロ経済ギャップの拡大は財政・金融政策などマクロ経済政策に関係していることは分かっていても、その量的関係は先行きの成長率やインフレ率の予想に左右されるので、予見し難い面がある。確かなことは、予想成長率や予想インフレ率が高まれば、一定のマクロ需給ギャップに対応するインフレ率は高まるし(デフレ率は縮小するし)、現実の需給ギャップの縮小も早くなるということだ。
日本の消費者物価インフレ率と実質GDP需給ギャップを描くと、下図の通りである。インフレ率と需給ギャップは同じように変動し、両者に相関関係があることを示している。しかし、1990年代にはインフレ率が需給ギャップの上に在り、2000年代は両者がほぼ同じ水準である。つまり、同じ需給ギャップ拡大の下で、1990年代のインフレ率の方が2000年代のインフレ率よりも高かった。
【インフレ率の構造的下方シフトは賃金上昇率の構造的下方シフトが一因】
このようなインフレ率の構造的下方シフト(デフレ化)については、いろいろな仮説が考えられる。一つは規制緩和・グローバル化に伴う内外価格差の縮小である。もう一つは、マクロ需給ギャップに対応した賃金上昇率が、下方シフトしたことである。下図のように、2000年代に入って企業収益は上昇しているが、雇用者報酬は低迷している。これは賃金の低い非正規雇用の増加、賃金より雇用を優先する日本型労働慣行などが背景にあると思われる。
【予想成長率と予想インフレ率の引き上げにデフレ克服の成否が懸る】
賃金上昇率の構造的下方シフトを一つの背景とするインフレ率の構造的下方シフト(デフレ化)に大きく絡んでいる要因として、最後に指摘すべきことは、日本の企業の予想成長率と予想インフレ率の下方シフトである。
予想成長率が下方シフトしたために、以前と同じ需給ギャップの下でも、以前ほどには投資と雇用を積極化しない。予想インフレ率が下方シフトしたために、以前と同じ需給ギャップの下でも、以前ほどには賃金を引き上げない。
従って、前述した政府と日本銀行の成長戦略は、核となる成長戦略産業の予想成長率に働きかけ、企業の投資・雇用・賃上げマインドを前向きに変えることができるかどうかに、成否が懸っているといえよう。