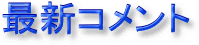
6寧抁娤丒暷崙棙忋偘偲挻嬥梈娚榓偺乽弌岥乿乮H16.7.2)
亂夞暅偺懕偔擔杮宱嵪偲棙忋偘孹岦偑巒傑偭偨暷崙宱嵪亃
6寧挷嵏偺乽擔嬧抁娤乿偼丄摉柺偺擔杮偺宨婥夞暅帩懕傪偼偭偒傝偲帵偟偨丅偲偔偵戝婇嬈惢憿嬈偺夞暅偑尠挊偱偁傞丅乽嬈嫷敾抐DI乿偼戝偒偔夵慞偟偰慜夞乮00擭9丄12寧乯偲慜乆夞乮97擭6寧乯偺僺乕僋傪挻偊丄杮擭搙偺愝旛搳帒偼慜擭斾亄20.4亾偲戝偒偔怢傃傞寁夋偱偁傞丅
偟偐偟丄拞寴丒拞彫婇嬈偲旕惢憿嬈偺夞暅偼丄乽嬈嫷敾抐DI乿傕愝旛搳帒寁夋傕偦傟掱戝偒側傕偺偱偼側偄丅埶慠偲偟偰丄桝弌偲桝弌娭楢愝旛搳帒偵儕乕僪偝傟偨夞暅偲偄偆惈奿偼曄傢偭偰偄側偄丅撪廀偑帺棩揑夞暅偵揮偠丄旕惢憿嬈丄拞寴丒拞彫婇嬈丄抧曽宱嵪偑棫捈傞挍偼側偄丅
乽嬈嫷敾抐DI乿傪広搙偵巊偆偲丄崱夞偺宨婥偺挿偝偼慜夞傪嬐偐偵挻偊偨偑丄慜乆夞暲傒偵払偡傞偵偼丄柧05擭偺拞崰枠夞暅偑懕偐側偗傟偽側傜側偄丅
愜偟傕暷崙偺岞掕曕崌偲FF儗乕僩偑0.25亾堷忋偘傜傟偨丅峏偵2.5亾偺堷忋偘偑8寧偵幚巤偝傟傞偲偄偆娤應偑嫮偄丅擭枛傑偱僕儕僕儕忋徃偡傞壜擻惈傪巜揈偡傞惡傕偁傞丅偲偔偵戝摑椞慖嫇偺寢壥柉庡搣惌尃偵曄傢傞偲丄棃擭偐傜嵿惌丒嬥梈椉柺偺嬞弅巔惃偑嫮傑傞偲偄偆偺偑丄戝曽偺尒曽偩丅
亂嬥梈挻娚榓偐傜偺乽弌岥乿偑栤戣偲側傞巐偮偺働乕僗亃
偙偺傛偆側擔杮宱嵪偺夞暅帩懕偲暷崙嬥棙偺忋徃孹岦偐傜敾抐偡傞偲丄崱屻丄嫲傜偔偼棃擭埲崀丄擔杮嬧峴偑尰嵼偺嬥梈挻娚榓偺廋惓乮偄傢備傞弌岥乯傪敆傜傟傞帠懺丄偁傞偄偼彮側偔偲傕嬥梈挻娚榓傪懕偗偰傛偄偐偳偆偐偺専摙傪敆傜傟傞帠懺偑廫暘峫偊傜傟傞丅偦偺僔僫儕僆偼丄戝偒偔暘偗偰丄師偺巐偮偺働乕僗偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傞丅
[働乕僗嘥]
乽抁娤乿偺攧忋崅寁夋乮慜擭搙幚愌亄0.7亾丄杮擭搙寁夋亄1.4亾乯偑帵嵈偡傞傛偆側宨婥夞暅偑杮擭搙拞偵懕偒丄2003擭搙偺3.2亾惉挿偵懕偒丄2004擭搙傕3亾戜偺幚幙惉挿棪偲側傞応崌丅2擭楢懕偺3亾戜惉挿偵敽側偄丄GDP儀乕僗偺廀媼僊儍僢僾偼2乣3亾弅彫偟丄慡崙CPI乮彍偔惗慛怘昳乯偺僀儞僼儗棪偼尰嵼偺儅僀僫僗0.3亾掱搙偺僨僼儗偐傜丄柧擭偵岦偭偰僾儔僗0.5亾慜屻偵忋徃偟偰偔傞偱偁傠偆丅偙傟偵敽側偄柤栚惉挿棪傕3亾戜偲側傝丄挿婜巗応嬥棙偼彮側偔偲傕3亾戜傑偱忋徃偟偰棃傞丅
亂奀奜嬥棙崅傗桝擖尨擱椏抣忋偑傝偺塭嬁亃
[働乕僗嘦]
杮擭壓婜埲崀偺奀奜丄偲偔偵暷崙偺嬥棙忋徃偵偮傟偰丄擔杮偺挿婜巗応嬥棙傕崙嵺揑嬥棙嵸掕傪捠偠偰忋徃偟丄杮擭壓婜拞偵3亾偵嬤晅偄偰棃傞働乕僗丅偙偺応崌偼丄挿婜嬥棙偺忋徃傗偦傟偵敽側偆姅壙偺夞暅掆懾丄懳暷桝弌偺撦壔側偳偐傜丄2004擭搙屻敿偵惉挿偼尭懍偟丄柧擭偵側偭偰傕CPI乮摨乯偺僀儞僼儗棪偼宲懕揑偵慜擭斾僾儔僗偲偼側傜偢丄僨僼儗扙媝偑偼偭偒傝偟側偄働乕僗偲側傠偆丅
[働乕僗嘨]
拞崙偵偍偗傞婎慴帒嵽偺儃僩儖僱僢僋丒僀儞僼儗傗拞搶偺抧惌妛揑儕僗僋偵敽側偆尨桘壙奿偺崅巭傑傝側偳偐傜丄擔杮偺尨擱椏偺壙奿偑忋徃傪懕偗丄僐僗僩丒僾僢僔儏偵傛偭偰CPI乮摨乯偺僀儞僼儗棪偑僾儔僗偵揮偠丄挿婜嬥棙傕3亾偵岦偐偭偰忋徃偟偰偔傞働乕僗丅
偙偺応崌丄僐僗僩丒僾僢僔儏偲挿婜嬥棙忋徃偼婇嬈廂塿傪埑敆偡傞偺偱丄惉挿偼棃擭偵岦偭偰尭懍偟偰偔傞偱偁傠偆丅
亂僨僼儗壓偺帒嶻僀儞僼儗偺儕僗僋亃
[働乕僗嘩]
働乕僗嘥偺応崌傎偳偼惉挿棪偑崅偔側偄偨傔丄廀媼僊儍僢僾偺弅彫偼戝偒偔側偔丄廬偭偰CPI乮摨乯偺僀儞僼儗棪傕僛儘亾慜屻偱僨僼儗扙媝偼偼偭偒傝偟側偄偑丄抧壙傗姅壙側偳偺帒嶻壙奿偑忋徃偟巒傔傞応崌丅
偙傟偼1980擭戙屻敿偲帡偨働乕僗偱偁傞丅偁偺帪偼丄CPI乮摨乯偺僀儞僼儗棪偼0.5亾掱搙偱偁傝丄暔壙偼嬌傔偰埨掕偟偰偄偨偑丄嬥梈挻娚榓偺壓偱帒嶻壙奿偺朶摣偲偄偆宍偱僶僽儖偑敪惗偟偨丅
偙偺働乕僗嘩偼丄崱屻擔杮嬧峴偑捈柺偡傞壜擻惈偺偁傞僔僫儕僆偺偆偪偱丄惌嶔揑懳墳偑嵟傕擄偟偄働乕僗偱偁傞丅
埲忋偺働乕僗嘥乣嘩偼丄昁偢偟傕撈棫偟偰尰傟傞栿偱偼側偔丄幚嵺偵偼嘥偲嘨偺擇偮偺働乕僗傗嘦偲嘩偺擇偮偺働乕僗偑廳側偭偰尰傟傞応崌傕偁傝偆傞偙偲偱偁傞丅
亂僀儞僼儗棪傪嬥棙忋徃偺儊儖僋儅乕儖偵偡傋偒働乕僗亃
偝偰丄偙偺巐偮偺働乕僗偵懳偡傞擔杮嬧峴偺揔愗側懳墳偼丄偳偆嵼傞傋偒偐偲偄偆乽弌岥乿榑傪峫偊偰傒傛偆丅
[働乕僗嘥]
偙偺応崌偼丄嬥梈挻娚榓傪廋惓偡傋偒偙偲偼尵偆傑偱傕側偄偑丄栤戣偼偦偺傗傝曽偱偁傞丅巗応偑夁搙偵斀墳偟偰挿婜嬥棙偑憗偔偐傜忋傝夁偓傞偲丄愜妏偺帩懕揑惉挿偵僽儗乕僉偑偐偐傞丅斀懳偵廋惓偑抶傟偰偟傑偆偲丄僀儞僼儗棪偑夁搙偵崅傑傝丄嫮偄堷掲傔偑昁梫偵側偭偰丄偙傟傕帩懕揑惉挿傪夡偟偰偟傑偆丅
偦偙偱弌偰偔傞媍榑偑丄乽僀儞僼儗栚昗抣乿偺愝掕偱偁傞丅擔杮嬧峴偑梊傔栚昗偲偡傞僀儞僼儗棪傪帵偟偰偍偗偽丄巗応偑夁戝丄偁傞偄偼夁彫偵斀墳偡傞偙偲偼側偄偱偁傠偆丄偲偄偆峫偊曽偩丅
偙傟偼丄乽堦掕偺僾儔僗偺僀儞僼儗棪乿傪嬥梈挻娚榓偐傜偺乽弌岥乿偺偄傢偽乽廫暘忦審乿偲偡傞傕偺偩丅
偟偐偟偙傟偼丄屻偵弎傋傞傛偆偵丄働乕僗嘨傗働乕僗嘩偺帪偵丄乽弌岥乿偑憗夁偓偨傝抶夁偓偨傝偡傞儕僗僋傪敽側偆偙偲偵側傞丅
廬偭偰丄栚昗抣偲偄偆宍偱偼側偔丄擔杮嬧峴偑梊憐偟偰偄傞僀儞僼儗棪傪巗応偵抦傜偣丄夁搙偺挿婜嬥棙忋徃傪梷偊傞岺晇偑梫傞丅
亂僨僼儗扙媝偑側偄尷傝摦偔傋偒偱偼側偄働乕僗亃
[働乕僗嘦]
奀奜嬥棙崅偺塭嬁偱擔杮偺挿婜嬥棙偑忋徃偟偰偒偨帪偵偼丄擔杮嬧峴偼偳偆懳墳偡傋偒偱偁傠偆偐丅
僨僼儗傪扙媝偟偰偄側偄帪偵丄奜惗揑梫場偱挿婜嬥棙偑忋徃偟丄惉挿偵埆塭嬁傪梌偊傞偺偼杊偑側偗傟偽側傜側偄丅偟偐偟丄抁婜嬥梈巗応偵偍偗傞挻娚榓傪峏偵恑傔偰傒偰傕丄抁婜嬥棙偼傕偆僛儘埲壓偵偼壓傜側偄偺偱丄挿婜嬥棙梷惂偺岠壥偼弌側偄丅
戝愗側偙偲偼丄挿婜嬥棙偺忋徃偑擔杮嬧峴偺嬥梈挻娚榓偺乽弌岥乿偺巒傑傝偱偼側偔丄傕偭傁傜奀奜梫場偵傛傞傕偺偩偲偄偆擔杮嬧峴偺擣幆傪丄柧妋偵巗応偵揱偊傞偙偲偱偁傠偆丅偦偺帠傪懺搙偱帵偡偨傔偵丄挿婜嬥棙堷壓偘偺岠壥偼堦帪揑側傕偺偵夁偓側偄偲偟偰傕丄挿婜崙嵚偺攦僆儁妟傪憹傗偡偺偑丄堦偮偺曽朄偐傕抦傟側偄丅偟偐偟挿婜揑側岠壥偺側偄惌嶔偱偁傞偐傜丄偁傑傝戝検偵幚巤偟側偄曽偑傛偄丅
亂僀儞僼儗栚昗抣偑晄揔愗偲側傞僐僗僩丒僾僢僔儏偺働乕僗亃
[働乕僗嘨]
偙偺僐僗僩丒僾僢僔儏丒僀儞僼儗偺応崌偼丄CPI乮摨乯偺僀儞僼儗棪偑僾儔僗偵側傞偺偱丄乽僀儞僼儗栚昗抣乿傪宖偘偰偄傞偲丄乽栚昗抣乿偵払偟偨偺偱偁傞偐傜摉慠嬥梈挻娚榓偐傜偺乽弌岥乿偩偲巗応偼敾抐偟丄挿婜巗応嬥棙偼忋徃偵揮偠傞丅
偙偺嬥棙忋徃偼丄偨偩偱偝偊僐僗僩丒僾僢僔儏偱廂塿傪埑敆偝傟偰偄傞婇嬈偵偲偭偰丄擇廳偺廂塿埑敆梫場偲側傞丅偙傟偼柧傜偐偵帩懕揑惉挿偺朩偘偲側傞憗夁偓傞乽弌岥乿偩丅
偙偺偙偲偐傜暘偐傞傛偆偵丄乽僀儞僼儗栚昗抣乿傪乽弌岥乿偺乽廫暘忦審乿偲偟偰宖偘偰偄傞偲崲偭偨偙偲偵側傞働乕僗偑偁傞偺偱丄乽栚昗抣乿愝掕偼揔愗側惌嶔塣塩偲偼尵偊側偄丅
偨偲偊僀儞僼儗棪偑僾儔僗偵揮偠偨偲偟偰傕丄偦傟偩偗偱嬥梈挻娚榓偺廋惓傪巒傔傞偲偼尷傜側偄偲偄偆偙偲傪丄擔杮嬧峴偼偼偭偒傝偝偣偰偍偄偨曽偑傛偄丅
亂僨僼儗壓偺帒嶻僀儞僼儗偺働乕僗亃
[働乕僗嘩]
CPI乮摨乯偺僀儞僼儗棪偑儅僀僫僗傪偼偭偒傝扙偟偰偄側偄偺偵丄搚抧傗姅幃側偳偺帒嶻壙奿偑偳傫偳傫忋徃偟巒傔偨帪偵偼丄擔杮嬧峴偼偳偆偡傋偒偱偁傠偆偐丅
帒嶻僀儞僼儗偼丄帒嶻偺捓戄椏乮椺偊偽壠捓丄抧戙乯側偳傪捠偠偰嵿丒僒乕價僗偺僀儞僼儗偵揮壔偡傞偲棟榑揑偵偼峫偊傜傟傞偑丄1980擭戙屻敿偺宱尡偵傛傟偽丄偦偺僞僀儉丒儔僌偼堄奜偲挿偄傕偺偱偁傞丅87乣89擭偺帒嶻僶僽儖偼丄偦傟偑曵夡偡傞89乣91擭崰偵側偭偰丄CPI乮摨乯偺僀儞僼儗棪偵攇媦偟偰偒偨丅
廬偭偰丄CPI乮摨乯偺僀儞僼儗棪偑僾儔僗偵側傜側偄尷傝丄挻娚榓傪懕偗傞偲偄偆懺搙傪偲傞偲丄僶僽儖偺敪惗偲曵夡偱帩懕揑惉挿偑夡傟傞儕僗僋偑偁傞丅
偮傑傝丄乽僀儞僼儗栚昗抣乿傪乽弌岥乿偺乽廫暘忦審乿偱偼側偔乽昁梫忦審乿偲偟偰偄偰傕丄乽弌岥乿偑抶傟傞偲偄偆嬥梈惌嶔偺幐攕傪斊偡儕僗僋偑偁傞偙偲偵拲堄偡傞昁梫偑偁傞丅
偙偺応崌偼丄偨偲偊僨僼儗偺扙媝偑偼偭偒傝偟偰偄側偔偰傕丄擔杮嬧峴偼挻娚榓傪廋惓偡傞桬婥傪帩偨側偗傟偽側傜側偄丅
亂僀儞僼儗棪傪嬥梈惌嶔塣塩忋偺乽嶲徠抣乿偲偣傛亃
埲忋丄峫偊傜傟傞巐偮偺働乕僗偵偮偄偰丄乽弌岥乿榑傪峫偊偨丅
堦偮偺寢榑偼丄乽僀儞僼儗栚昗抣乿傪宖偘傞偙偲偼丄乽弌岥乿偺乽廫暘忦審乿偲偟偰偼栜榑偺偙偲丄乽昁梫忦審乿偲偟偰傕丄晄揔愗偱偁傞偲偄偆働乕僗偑懚嵼偡傞偙偲偩丅働乕僗嘥傗働乕僗嘦偺帪偼傛偄偑丄働乕僗嘨偱偼乽弌岥乿偑憗夁偓丄働乕僗嘩偱偼乽弌岥乿偑抶夁偓傞偐傜偩丅
偟偐偟丄僀儞僼儗棪傪柍帇偟偰傛偄栿偱偼側偄丅働乕僗嘥偲働乕僗嘦偱偼丄擔杮嬧峴偑CPI乮摨乯偺僀儞僼儗棪傪戝愗側乽嶲徠抣乿偵偟偰偄傞偲偄偆擣幆偑丄夁搙偺挿婜嬥棙曄摦偲丄偦偺宱嵪偵懳偡傞奾棎揑塭嬁傪杊偖忋偱廫暘偵栶偵棫偮丅
嵟嬤擔杮嬧峴偺憤嵸傗暃憤嵸偺堦恖偑丄彨棃偼丄擔杮嬧峴偑朷傑偟偄偲峫偊偰偄傞僀儞僼儗棪傪惌嶔塣塩偺乽嶲徠抣乿偲偟偰岞昞偡傞偙偲傕峫偊傜傟傞偲敪尵偟偰偄傞偑丄傕偟偦偺堄枴偑偙偙偱弎傋偨偙偲偲摨偠偱偁傞側傜偽丄巹偼僒億乕僩偟偨偄偲巚偆丅
亂巐偮偺働乕僗偵懳偡傞奺奅偺斀墳亃
巐偮偺働乕僗偵懳偟偰擔杮嬧峴偑埲忋偺傛偆側惌嶔懺搙傪偲偭偨帪丄崙柉丄嶻嬈奅丄嵿柋徣偼偳偺傛偆偵姶偠傞偱偁傠偆偐丅
[働乕僗嘥]
偙偺働乕僗偼宨婥夞暅偲偦傟偵敽側偆暔壙忋徃偵尒崌偭偨嬥棙忋徃偱偁傞偐傜丄奺奅偺晄枮偼彮側偄偱偁傠偆丅宱嵪奅偲嵿柋徣偼嬥棙晧扴偺憹壛傪寵偑傞偱偁傠偆偑丄廂塿偺夞暅傗帺慠憹廂偑偁傞偺偱丄嫮偄斀敪偼側偄偱偁傠偆丅
[働乕僗嘦]
嬥梈挻娚榓偑懕偔偺偱宱嵪奅偲嵿柋徣偵晄枮偼側偄偱偁傠偆偑丄徚旓幰偱偁傝梐嬥幰偱偁傞崙柉偐傜尒傞偲丄暔壙忋徃壓偱嬥棙偑悩抲偐傟傞偙偲偵晄枮偑崅傑傠偆丅
[働乕僗嘨]
宱嵪奅偲嵿柋徣偼暷崙偵偮傜傟偰嬥棙偑忋徃偡傞偙偲偵晄枮偼偁傠偆偑丄擔杮嬧峴偼偦傟傪梷偊傛偆偲偟偰偄傞偺偱偁傞偐傜丄擔杮嬧峴偵岦偭偰嫮偄晄枮偼棃側偄偱偁傠偆丅梐嬥幰偵偼晄枮偑偁傞偐傕抦傟側偄丅
[働乕僗嘩]
崙柉偼偙偺棙忋偘傪巟帩偡傞偱偁傠偆偑丄嬥棙晧扴偑憹偊傞宱嵪奅偲嵿柋徣偵偼晄枮偑偁傞偐傕抦傟側偄丅偙偺働乕僗偑堦斣傗偭偐偄偱偁傠偆丅
埲忋偺傛偆偵丄擔杮嬧峴偺惌嶔懺搙偑奺奅偐傜婌偽傟傞働乕僗偼堄奜偲彮側偔丄偙偺応崌偼働乕僗嘥偟偐側偄丅偙傟偑拞墰嬧峴偺廻柦偱偁傞丅嵟廔揑偵偼擔杮宱嵪偺帩懕揑惉挿偵帒偡傞偺偱丄奺奅偐傜昡壙偝傟傞偲妋怣偟丄擔杮嬧峴偼桬婥傪帩偭偰幚峴偡傞傎偐偼側偄丅
![]()