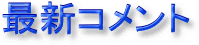
金融行政は介入型から市場型へ戻れ(H16.3.26)
【矛盾する三つの数量目標】
日本の金融行政は、米国から迫られている「不良債権の早期処理」と、BIS規制である「自己資本比率規制」を最優先にし、自己資本比率が低下した銀行には公的資本を注入し、「効率性指標」の目標化を義務付けている。
しかし、「不良債権比率」と「自己資本比率」と「効率性指標」の三つの数量目標は、本来相互に矛盾する。不良債権処理を急げば、その年の業務純益だけでは処理の資金が足りなくなり、資本金を取崩すから自己資本比率が下がる。不良債権処理(とくにオフ・バランス化)を急げば、不良債権を割引して市場に売却したり、貸倒れ償却にしたりするので、これらの信用コストを業務純益から差し引いた当期純益は赤字になり、効率性指標は悪化する。そこで自己資本比率と効率性指標の低下を最小限に抑えようとすれば、二つの指標の分母である貸出総額を圧縮するほかはない。つまり、収益性が低いと思われる貸出を減らして行くのだ。その結果「貸し渋り」や「貸しはがし」が起きて景気に悪影響が及ぶ。また自己資本比率を高めようとすれば、一定の資金で貸出を拡張する「信用拡張係数」が下がるので、利益を挙げる上で制約となる。ここでも、自己資本比率と効率性が矛盾している。
これでどうして銀行システムが蘇り、日本経済が復活するのか。結果は逆ではないか。
【九〇年代前半が不良債権早期処理の好機だった】
経済回復にとっては、不良債権が有るよりも無い方がよいに決っている。しかし、今の日本の銀行経営にとって、不良債権処理は何よりも優先すべき課題なのか。
「バブルの崩壊」のような一回限りの原因で大量の不良債権が発生した時には、たとえ期間損益が赤字になっても、自己資本比率が低下しても、業務純益の全額投入と自己資本の取崩しで、一挙に不良債権を処理すべきである。何故なら、処理した後、一回限りの原因は終っているので、不良債権は再び発生しない。赤字決算も自己資本比率低下もその期限りで終り、次期から決算は黒字に戻り、自己資本は増資で補える。市場も顧客もそう考える。銀行に危機は訪れない。
アメリカ、イギリス、スウェーデンなどの不良債権早期処理がそのいい例である。これらの国々では、不良債権の早期処理に成功し、銀行は蘇ってその後の経済成長を支えた。
日本でも、「バブル崩壊」直後の一九九〇年代前半であれば、この理屈が成り立った。事実、九二年頃から、大手銀行は不良債権の早期処理を考え始めた。
それに「待った」をかけたのは、大蔵省である。
この事件は、後に「NHKスペシャル」に取上げられ、ドキュメンタリーとして放映された。一九九二年、三和銀行は「日住金」(三和をメイン・バンクとする住宅専門金融機関〈住専〉の一つ)に対する不良債権を一挙に処理する腹を固め、「日住金」に対して不良債権を持つ他の銀行にはかった。「日住金」は倒産させ、返済されない貸出金は、貸倒れ償却して損金処理をしようとしたのである。
会議はその方向に進んでいたが、大蔵省は会議に参加している大銀行の頭取に直接電話をかけて、「信用不安を起こすといけないので、不良債権の早期処理案に反対するよう」圧力をかけた。「NHKスペシャル」では、会議に出席していた各大銀行の役員が、一人また一人と議場外に電話で呼び出され、頭取から方針を変更して早期処理案に反対せよという指示を直接受ける。会議の方向はにわかにおかしくなり、遂に早期処理案は否決されてしまう。
もしこの時、一九九二年頃、「住専」に対する不良債権が早期処理され、更に他の不良債権の処理に取りかかっていたならば、二一世紀の初頭に俗に百兆円と言われる程にまで不良債権は膨張しなかったであろう。しかし日本では、不良債権早期処理の絶好の時期を逃してしまった。先送りされた不良債権は、どんどん膨らんだ。
大蔵省は目先の小さな信用不安を恐れて、逆に大きな信用不安の種を作り、九〇年代後半以降に持越したのである。
【持越されて新たに膨張した不良債権】
一九九六年になると、遂に住専の経営が身動き出来ない程にまで不良債権が膨らんでしまった。そこで橋本政権は、六八五〇億円の公的資金(国民の血税)を投入して、住専問題の解決を図った。住専は、国民から預金を受け入れて資金運用をする機関(いわゆる預金銀行)ではなく、銀行など他の金融機関から資金を借入れて、不動産関係などに融資する普通の金融業(ノンバンク)である。従って、六八五〇億円は、その後の公的資金投入のように預金者を救うためではない。住専に対する貸し手金融機関を救うための資金であった。
実際には、住専に対する貸し手の銀行は、その貸出債権の多くを切り捨てて損金処理をし、損失を負担した。しかし、住専に貸していた農林系統金融機関に対して、この六八五〇億円の国民の血税を回し、その経営を救済する形となった。住専は、この資金で農林系統金融機関からの借入を返したからである。
この処理が終った後、橋本政権は、不良債権問題は峠を越したと述べた。しかし実際には、住専に対する銀行の不良債権は、銀行全体の不良債権のほんの一角にすぎなかった。銀行は住専以外の多くの顧客に対して、百兆円近い不良債権を持っていたのである。
このようにして政府と大蔵省は、一九九〇年代前半に早期処理をすればこれ程の大事に至らなかった不良債権問題を、二一世紀にまで持越したのである。
【不良債権問題の変質で早期処理は不適切に】
その事によって、不良債権問題の本質が変わった。不良債権は、「バブルの崩壊」という一回限りの原因によるものから、一〇年以上の経済停滞による一般企業の「経営悪化」によるものに変質していった。
同時にその事によって、不良債権を一挙に早期処理をするという対策は、不適切になった。何故なら、本業以外の不動産や株の投機による損失=不良債権であれば、それを切り捨てて身軽になることによって、本業が活きてくる。企業が復活する。しかし、本業そのものが一〇年以上の経済停滞で悪化し、損失=不良債権が発生している場合は、不良債権を切り捨てても本業が立直る保証はない。本業の再建計画が無い限り、企業は立直れないし、不良債権は再び増えてくるので、その早期処理は対策にならない。
むしろ、不良債権の処理をやみくもに急げば、経済の長期停滞で一時的に赤字を出している企業、正常な経済なら日本経済を担って行くべき中堅・中小企業を、潰してしまう恐れがある。
日本経済の長期停滞がここ迄続くと、不良債権の処理を最優先にするのは正しい政策ではない。経済が持続的成長軌道に乗れば蘇り、日本経済を支えて行く企業、とくに中堅・中小企業を潰してしまう。銀行にとっても、将来の収益源となる大切な顧客を失ってしまう。
今の段階では、不良債権の処理は、将来を見据えた銀行の総合的経営戦略の一環として考えるべきことで、その決定は銀行自身の自己責任に委ねるべきである。行政当局が一律に強制すべきことではない。この事は、後にもう一度触れる。
【日本の銀行を狙ったBIS規制】
同じことは、自己資本比率規制についてもあてはまる。
そもそも自己資本比率規制は、BIS(国際決済銀行)による一九八八年一二月の「銀行の自己資本比率規制に関するバーゼル合意」(いわゆる「BIS規制」)に基づき、日本の銀行に一九九三年三月から適用されたものだ。国際市場でも活動する銀行は八%以上、国内でのみ活動する銀行は四%以上、の自己資本比率規制が日本の銀行に課せられた。
BIS規制が決められた一九八八年は、バブルの絶頂期で、日本の銀行が世界一〇大銀行の地位を独占し、国際市場で大活躍をしていた。そのやり方は、市場で大量の外部資金を調達し、薄い利鞘で貸出しに回す形でプレゼンスを高めたのである。このように、市場調達の外部資金に依存して拡大する日本の銀行は、伝統的に自己資本比率が低かった。
そこを欧米の銀行に狙われた。国際金融市場の安定性を確保するという大義名分の下に、欧米各国が一致して、八%の自己資本比率規制の導入を提案してきた。外部資金に依存した日本の銀行の貸出拡張に制約を課するためで、この自己資本比率規制を満たさない銀行は、国際金融市場での活動を禁止しようというのである。
日本の銀行にとって不幸であったのは、このBIS規制の適用開始が、バブル崩壊後の一九九三年三月以降となったことだ。ただでさえ低い自己資本比率が、株価(含み益の四五%は自己資本とみなせる)の暴落によって更に低下した。
その上、業務純益では間に合わない程多額の不良債権処理をするとなると、自己資本を取り崩さざるを得ず、ますます自己資本比率は下がる。大手銀行を残して、ほとんどの銀行は国際金融市場から閉め出された。八%ではなく、四%の自己資本比率規制で済むからだ。それでも足りず、比率の分母を圧縮するための「貸し渋り」「貸しはがし」となった。
【自己資本比率は銀行が決めるもの】
そもそも自己資本比率は、このように当局によって強制されるべきものであろうか。
銀行のリスク管理は、経営戦略によってさまざまな形をとる。
例えば、リスクは高いが高収益の期待出来る投資銀行業務を主とする銀行は、高い自己資本比率を保たないと市場から信用されないかも知れない。逆に、コストのかかる高度なリスク管理体制を持たない銀行は、利鞘は薄いが十分にリスクが分散される安全な貸出を中心に小売銀行業務に徹するかも知れない。この場合は、自己資本比率は低くてもよいと考えるであろう。
自己資本比率が低ければ、信用拡張係数が高くなるので、薄利多売の経営戦略がとれる。小売銀行型である。反対に自己資本比率が高いと信用拡張係数が低いので、ハイリスク・ハイリターンを狙う卸売銀行型になる。
このように、自己資本比率というものは銀行の経営戦略と表裏の関係にあり、リスクとリターンの組合わせによって、さまざまの最適水準がある。この複雑な銀行の経営に対して、単一の自己資本比率を行政側が規制として強制するのは無理がある。これは過剰な「介入行政」である。
銀行のリスクとリターンに関する経営戦略、それに対応したリスク管理体制と自己資本比率、結果として出て来る収益率と不良債権比率、これらは全部銀行が自己責任で選択すべき事である。そして、その適否を判定するのは、行政当局ではなく、市場であり顧客である。それによって株価が動き、顧客の数が決まる。その「結果責任」を経営者がとる。
行政当局の仕事は、自己資本比率、収益率、不良債権比率に介入するのではなく、監督と検査によって、それらの諸指標に誤りがないかチェックし、その情報公開を促すことである。それ以上の経営介入をしてはならない。判定するのは「市場」であり「顧客」であって、「行政」ではない。
銀行の破綻も自己責任である。行政の仕事は、その破綻が決済システム全体の不安定化を招かないように十分な流動性を供給することと、一口一千万円以下の預金者を保護するペイオフの実施である。これが「市場型」の金融行政である。
日本の金融当局は、二〇〇六年三月に導入を予定して、現在進行中のバーゼル合意(BIS規制)見直しの国際論議の中で、一律の自己資本比率規制の撤廃を主張すべきである。「介入型」から「市場型」へ銀行監督の在り方を変えようというのは、世界の潮流であり、その流れに沿って、日本の主張を堂々と打出すべきだ。
【過剰介入の金融行政を改め「市場型」に戻れ】
以上見てきたように、不良債権比率も自己資本比率も、銀行が自主的に決めるべき大切な経営戦略の一環である。そして最終的には、その結果が収益性指標に現れ、経営者が責任をとる。
この三つの指標、不良債権比率と自己資本比率と収益性指標(例えばROE〈自己資本収益率〉、ROA〈総資産収益率〉)は、既に詳しく述べたように相互に矛盾する。
本来矛盾する三つの経営指標について、行政が数値目標を強制するのは民間市場経済への「過剰介入」である。矛盾する三つの指標についてはいろいろな組合せがあり、そのどれが適切かということは行政が判断する問題ではないし、そもそも判断する能力もない筈だ。
この組合わせは、経営者がクビを賭けて選択し、顧客や株式市場の投資家など広い意味の「マーケット」に判定してもらうことである。行政が行うのは、三つの指標に偽りがないかどうかを検査して公表し、透明性を高めるところ迄だ。その結果、マーケットの判定で退場を余儀なくされる銀行については、預金者を保護し、決済システムの安定性を維持することに努めるのが行政の仕事である。やたらに国民の血税(公的資金)を投入して、銀行経営を救うのは、いいかげんにやめるべきだ。
このような「市場型」の金融行政に転換するならば、銀行経営者の自律性が高まり、銀行の差別化が進み、リスクを取って融資する銀行が現れ、日本経済の復活につながることになろう。
【日本の銀行が総合金融サービス業に脱皮する日】
日本の銀行が自主的に経営戦略を立て、新しい金融サービス業に脱皮するのは、いつであろうか。
大手銀行七グループの不良債権比率(金融庁公表ベース)は二〇〇二年三月の八・六%をピークに減り始めており、二〇〇三年九月には六・四%に下った。二〇〇五年三月に四%まで下げるという金融庁の目標は多分達成されるであろう。
しかし、三つの事に注意する必要がある。
第一に、四%自体、国際基準から言ってまだ高い。国際的な優良銀行のように二%以下になるのは、二〇〇七年頃までかかる。
第二に、これは平均の話であり、東京三菱や住友信託のような優良行は既に四%を割っている。反面、「りそな」のような銀行はまだかなり高い。平均で論じない方がよい。
第三に、全体の三分の一を占める地域銀行の不良債権比率は、二〇〇二年九月の八・三%をピークに低下し始めたが、改善のテンポは緩やかである。二〇〇三年九月末現在、まだ七・五%だ。ここでは格差が特に大きく、問題行が存在する。
不良債権の処理を急いでいる間は、銀行経営にとって一番大切な収益性指標が悪化する。銀行の業務純益の源泉は、貸出利鞘から経費率を差し引いたものである。それは黒字だ。しかし、不良債権処理で発生したコスト率、すなわち「実現信用コスト率」は、一九九四年(平成六年)度以降一%を大きく超えており、ピークの九八年(平成一〇年)度には五%近くに達している。最新の二〇〇三年度上期でも、まだ一・三六%である。
その結果、この実現信用コスト率を差し引いた「実質貸出利鞘(経費・実現信用コスト勘案後)」は、一九九三年(平成五年)度以降最近まで、一%〜六%弱の赤字である。
その上、各行は自己資本比率も維持するために、信用拡張を一定に抑えなければならないので、なかなか業務純益を増やせない。
日本の大手銀行が、欧米の大手銀行のように、ROE(自己資本収益率)で一五%〜二〇%、ROA(総資産収益率)で一・〇%〜一・五%という収益率を実現するためには、不良債権処理を進めて実現信用コストを大きく引下げるか、あるいは自己資本比率規制の撤廃を実現して、以前のように外部資金調達で業容を拡大し、貸出利鞘を大きくするしかない。しかし、いずれも直ぐには出来ない。
卸売銀行業務、小売銀行業務、信託銀行業務を併せ持った総合的な金融サービス業として、日本の銀行が国際的に進出するにはもう少し時間がかかる。
古いタイプの小売銀行業務の「敗戦処理」がまだ続いており、新しいタイプの卸売銀行業を含む総合的な金融サービス業を展開する余力はまだ日本の銀行にはない。またそれを可能にする金融業の垣根規制の撤廃も遅々としている。
ただし、大手行のうちの最優良行は、二〇〇五年三月までに実現信用コスト率を一%以下に下げ、「実質貸出利鞘」を黒字に転換することができるかも知れない。そのような優良行と大手の優良証券会社が合併して、国際的に比肩し得る総合的な金融サービス会社に脱皮することは、将来の問題として十分あり得る。
フロント・ランナーがそうなるためにも、日本の金融行政が「介入型」から「市場型」に早く変り、また銀行業と証券業の垣根規制を欧米並みに緩和することが望ましい。
取敢えずは、三菱東京グループがアコムを傘下に入れたように、小売銀行サービスの総合化が進んで行くであろう。
![]()